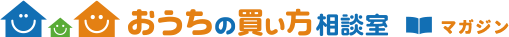家づくりの流れを徹底解説!住宅会社選びのポイントや工事期間も紹介
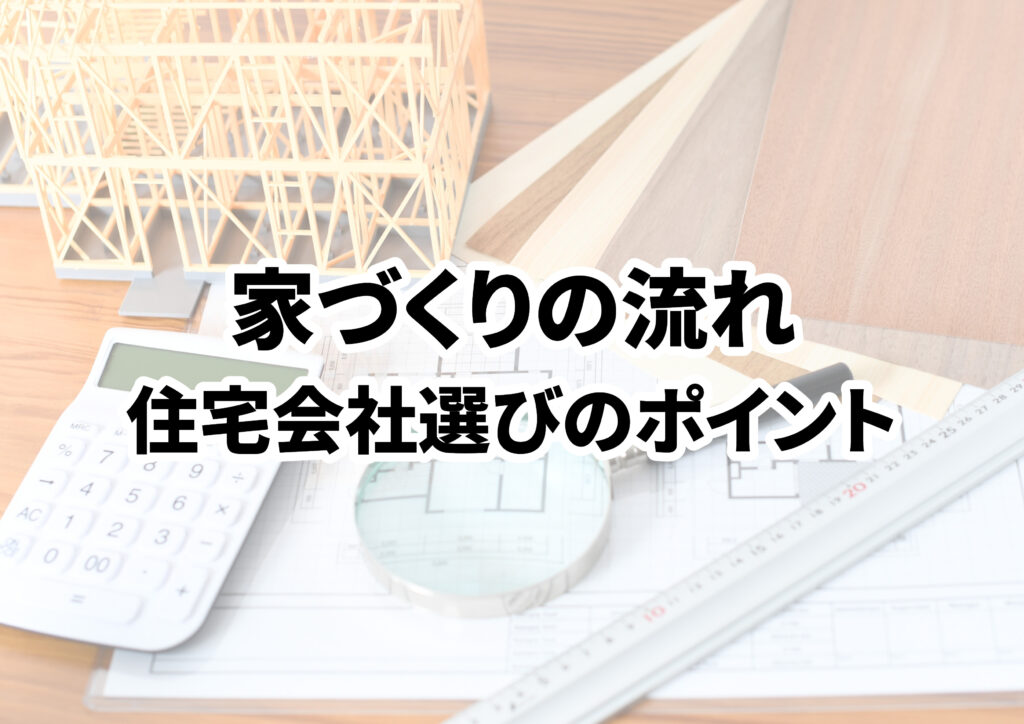
家づくりを考え始めたものの、「何から手をつければいいの?」「資金計画やスケジュールは大丈夫?」と、次々に疑問が浮かんでいませんか?初めての家づくりは、大きな決断が連続するため不安になりますよね。スケジュールや予算をあやまると、理想の間取りを諦めることになりますし、ローンの返済で苦しむ可能性も心配です。
そこで本記事では、おさえておきたい家づくりの基本的な流れを解説します。また、住宅会社選びや資金計画のコツ、トラブル回避のポイントも紹介しました。この記事を読めば、家づくりをかしこくスムーズに進められますよ。資金計画やスケジュールに余裕をもち、ストレスなく理想のマイホームを手に入れましょう。
家づくりの流れ1(準備・計画)
「家を建てたい!」と思ったら、まずは資金計画と情報収集からとりかかりましょう。失敗するリスクを減らし、理想の家づくりをスムーズに進めるためにも、このステップでしっかりと準備しましょう。
資金計画
家づくりの第一歩は、現実的な資金計画をたてることから始まります。具体的には、下記の金額をもとに住宅購入にかけられる金額を決めていきます。
- 住宅ローンの借入総額
- 毎月の返済額
- 頭金
ポイントは、「借入れ可能額」でなく、「無理なく返済できるか」という視点で計画を立てることです。一般的に住宅ローンの借入目安は年収の5〜7倍と言われていますが、人によって将来のライフイベント(子どもの教育費など)は様々です。
そのため資金計画は年収だけでなく、ご家庭のライフプランに合わせた長期的な視点で計画する必要があります。住宅購入する資金について「住宅購入で重要なライフプランシミュレーションをしてみよう」で詳しく解説しています。漠然とした不安を解消するためにも、ぜひシミュレーションを活用しましょう。
情報収集
理想の家づくりを実現するためには、幅広い情報収集が欠かせません。住宅展示場やモデルハウスの見学、インターネットでの検索(「地域名+工務店」など)を通じて、自分の希望や予算に合った会社を複数ピックアップしていきます。
あわせてSNSやウェブサイトから、多くの住宅スタイルや間取りのアイデアを集めましょう。ハウスメーカーや工務店のカタログや資料も参考になります。集めた情報をもとに、家族で「譲れない条件」について話し合い、マイホームのイメージを具体化していきます。
この段階で検討すべき重要ポイントは以下の4つです。
- 住宅タイプ(平屋・2階建て・一戸建てなど)
- 住宅スタイル(子育て重視・素材・庭の有無など)
- 立地条件(学校や交通機関の近さ)
- エリア(学区・通勤圏内)
気に入った住宅の写真や資料は保存しておくのがおすすめです。あとで工務店やハウスメーカーに自分のイメージを伝える際に役立ちます。
理想の住まい探しのコツや情報収集については「住まいの探し方!情報収集のコツや住宅購入時の注意点を解説」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
家づくりの流れ2(住宅会社選定~契約まで)
家づくりの計画がかたまったら、住宅会社選びから契約までの具体的なプロセスに入ります。この段階では、パートナーとなる住宅会社の選定・土地探し・住宅ローンの手続きなど、家づくりの土台となる重要な決断が続きます。丁寧に進めましょう。
住宅会社の選定
予算と集めた情報をもとに、一緒に家づくりを進めていく会社を決定します。満足できる家づくりを叶えるためにも、住宅会社は下記の視点で選びましょう。
- 費用が見合うかどうか(住宅会社の価格帯が予算と合うかどうか)
- 理想の家になりそうか(実績や強みなど)
- 信頼できるかどうか(口コミや担当者との相性)
- アフターフォローは手厚いか(保証・点検・メンテナンスなど)
住宅会社とは、この段階で仮契約をかわすのが一般的です。多くの場合、仮契約では10万円程度の申し込み金や手付金などが必要になります。この申込金は本契約時に請負契約の一部として充当されることが多いですが、仮契約後にキャンセルした場合は返金されないこともあるため注意が必要です。仮契約とはいえ、住宅会社は慎重に選んでくださいね。
住宅ローンの事前審査
住宅会社を決めたら、住宅ローンの事前審査を行います。事前審査は、年収や職業などの基本情報から簡易的に審査するもので、最短で当日、遅くとも1週間程度で結果が出ます。
事前審査をクリアしておくことで、いざ理想の土地が見つかった際にスムーズに手続きを進められますよ。無理のない返済プランの立て方は「住宅購入の資金計画で失敗しない!ローンの種類や選び方を解説」で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
土地の選定
下記の条件をもとに、土地選びを行います。
- 学区や通勤距離
- 周辺環境(スーパーや医療機関の有無)
- 災害リスク
- 治安
土地選びは、住宅会社を決めた後に行うのがおすすめです。土地を先に決めてしまうと、土地の法的規制や建築条件によって希望の家が建てられなかったり、予想外の追加費用が発生したりして後悔する可能性があります。
建物のプランニング・見積もり
間取りや外観デザイン、設備などの希望を住宅会社に伝え、プランを作成してもらいます。プランがかたまってきたら見積もりを依頼し、予算内におさまるかを確認します。予算オーバーの場合は、優先順位をつけて費用を調整しましょう。
計画を曖昧にしないためにも、「今すぐ必要なもの」と「後から追加・変更できるもの」を区別するのがおすすめです。後々の変更で工期の遅れや追加費用が発生する可能性を減らせます。
土地購入の申し込み
理想の土地が見つかり、建物プランと見積もりが確定したら、土地の買付申し込みを行います。買付申し込みは買付証明書への記入と押印のみで、この段階では金銭の支払いは発生しません。
好条件の土地は競争率が高く、すぐに買い手がつくことも多いため、気に入った土地があればなるべく早く申し込むことが大切です。値下げ交渉中に他の人から売り出し価格で申し込みがあると、交渉が白紙になる可能性もあるため注意しましょう。申し込みは、周辺環境や日当たり、前面道路の状況なども再確認し、納得してから行うようにしましょう。
土地の売買契約
買付申し込み後、不動産会社から重要事項説明を受け、内容に納得できれば土地の売買契約を締結します。手付金として、土地価格の5〜10%程度を現金で支払うのが一般的です。
手付金は後日、土地代金から差し引かれます。ですが買主が自己都合でキャンセルした場合、通常は返還されません。ただし、売主の都合による解約や契約違反の場合には返還されます。土地の契約は一生に何度もある機会ではありません。不明点はしっかり質問し、納得したうえで契約を結ぶことが大切です。
敷地調査や地盤調査
敷地調査や地盤調査は、基本的に土地購入後に行うのが一般的です。そのため、「地盤が弱いことが発覚し、改良工事に数十万必要になった」などのケースも起こりうるため注意が必要です。
購入前には、事前に周辺環境の地盤データをもとに地盤の強さをある程度予測してもらい、かかる費用を予想しておくようにしましょう。
建物の工事請負契約
住宅会社と建物の工事請負契約を締結する際は、以下の書類をしっかり確認しましょう。
- 工事請負契約書
- 設計書
- 仕様書
- 見積書
- 間取り図
契約後の大幅な変更は、工期の遅れや追加費用の発生につながります。契約前に曖昧なままにしておくと、後々トラブルの原因になりかねません。設備やオプションに不明点があれば、この段階で確認し、納得してから契約しましょう。
住宅ローンの本審査
工事請負契約の締結後、住宅ローンの本申し込みを行います。事前審査と異なり、本審査ではより詳細な収入証明書・住民票・印鑑証明書などの書類提出が必要です。
審査期間は金融機関によって異なりますが、1〜3週間程度かかるのが一般的です。金融機関や繁忙期によって異なるため、最大で1か月程度かかる場合もあります。審査に通過すると金銭消費貸借契約を締結し、住宅ローンが実行され土地代金の支払いや建物の着工資金が用意されます。つなぎ融資を選択した場合、この段階で土地代金の支払いが必要です。
家づくりの流れ3(契約~打ち合わせ完了)
この期間は理想の家を形にするための重要なプロセスです。住宅会社との契約を結んだ後は、家づくりの具体的な内容を決めていく詳細打ち合わせの段階に入ります。
詳細打ち合わせ
詳細打ち合わせでは、間取りや設備機器の細かな仕様を決定します。キッチンやお風呂などの水回り設備、床材や壁紙などの内装材、照明器具やコンセントの位置まで細部にわたって検討します。
生活動線をシミュレーションしながら打ち合わせを進めると、後悔が少なく快適な家になりますよ。家族の要望をリストアップし、優先順位をつけましょう。曖昧な要望は時間がかかるだけでなく、予算オーバーの原因にもなります。家事効率や収納計画、将来のライフスタイル変化も考慮して、担当者とじっくり話し合いましょう。
設計合意の締結
詳細打ち合わせが完了したら、設計合意の締結へと進みます。当初の契約内容からの変更点を含めた最終的な設計図面・仕様書・見積書を確認し、工事着工前の最終契約をかわします。追加工事や仕様変更の費用変動は、事前に把握しておきましょう。
確認を怠ると、引き渡し後のトラブルや想定外の費用発生につながります。納得がいかない点や疑問点は必ず質問し、理解したうえでの署名・押印が大切です。
家づくりの流れ4(着工~引き渡し)
いよいよ家づくりの最終段階である着工から引き渡しに向かいます。家が形になっていく様子を見られるため、家づくりの醍醐味を感じられるでしょう。工事の進捗を確認しながら、理想の我が家の完成を楽しみに待つ時期になります。
着工
着工の流れは以下のとおりです。
- 基礎工事
- 上棟(建物の骨組みが完成する工程)
- 外壁・屋根工事
- 内装工事
工事期間は一般的に4〜5か月程度です。定期的に現場を訪問し、進捗状況を確認すれば、イメージとのズレを早期に発見できます。工事中に気になる点や変更したい箇所があれば、早めに担当者に相談しましょう。完成後の修正は難しいため、早い段階での確認が重要です。
着工前には近隣住民への挨拶を行いましょう。事前の配慮が関係を円滑にし、工事中や入居後のトラブルが起こりにくくなります。
地鎮祭
地鎮祭は、着工前に行われる伝統的な儀式で、工事の安全と家の繁栄を祈願する意味があります。必ず行わなければならないものではありませんが、多くの方が実施している日本の伝統的な風習です。費用は3〜5万円程度が相場で、祭典費用と神主への謝礼が含まれます。地域によって風習が異なる場合もあるので、住宅会社に相談しましょう。
竣工検査・引き渡し・入居
工事が完了すると、竣工検査を経て引き渡しとなります。竣工検査では、施主自身が住宅会社の担当者と一緒に家の隅々までチェックします。壁や床の仕上がり、設備の動作確認など、気になる点があれば遠慮なく伝えましょう。
問題がなければ、住宅会社から鍵と保証書を受け取り、各設備の使用方法の説明を受けます。引き渡し確認書にサインをして、晴れてマイホームの引き渡しが完了です。引っ越しをして待望の入居となります。
家づくりにかかる期間
注文住宅の完成までにかかる期間は、一般的に8〜15か月程度です。
| 工程 | 所要期間 |
| 情報収集や予算計画 | 1~3か月 |
| 住宅会社選定から土地購入、プラン決定、契約 | 3~6か月 |
| 実際の建築工事 | 4~5か月 |
| 完成・引き渡し・入居準備 | 1か月 |
建築期間は家の規模や工法によっても変動します。たとえば、木造2階建ての一般的な住宅なら工事期間は4か月前後が目安ですが、自然素材や特殊な工法を採用すると長くなりがちです。
土地探しやプランニングに時間をかけたり、デザインにこだわったりしても、家づくりにかかる期間はさらに長くなります。家づくりは、入居希望時期から逆算して計画的に進めるようにしましょう。
家づくりのタイミング
家づくりを始めるタイミングは、人それぞれの状況によって異なります。
多くの場合
- 結婚や出産などでライフステージ変わるとき
- 経済的に見通しがたったおき
などをきっかけに、家づくりを検討する傾向があります。
「住宅購入はいつがベスト?家を買う時期やタイミングを解説」では、家を購入するベストタイミングの判断基準を解説しています。タイミングを間違えて後悔しないためにも、ぜひ参考にしてください。
【費用相場】家づくりに必要なお金
家づくりの費用は住宅の種類によって大きく異なります。住宅金融支援機構の「2022年度フラット35利用者調査」によると、住宅種別の平均費用は以下の通りです。
- 注文住宅:3,717万円
- 土地付注文住宅:4,694万円
- 建売住宅:3,719万円
- 新築マンション:4,848万円
- 中古戸建て:2,704万円
- 中古マンション:3,157万円
家づくりでは、これらの総額だけでなく、支払いのタイミングも重要です。土地購入時には手付金(土地価格の5〜10%程度)が必要になり、建物の工事請負契約時にも契約金が発生します。
地盤調査や地盤改良工事、登記費用、印紙税、引っ越し費用なども計上しておきましょう。
「家づくりでいつ、いくらのお金が必要なのか」を具体的に把握したい方は「住宅購入で必要なお金をシミュレーションしよう!~住宅ローン・現金一括~」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
家づくり の注意点
家づくりを進める過程では、多くの場面で判断を迫られます。当初の計画通りに進まないことも少なくありません。スムーズで後悔のない家づくりを実現するためには、以下の注意点に気を配りましょう。
- 入居希望日から逆算して計画する
- 追加費用を考慮する
- 優先順位をつける
入居希望日から逆算して計画する
マイホームの完成時期は、入居希望日から逆算して計画するのが効果的です。進学や転勤などの重要なライフイベントに合わせて入居したい場合はとくに重要です。
一般的に土地探しから入居まで約1年かかるため、余裕をもった計画にしましょう。地盤改良工事が必要になったり、天候不良で工事が遅れたりすることも珍しくありません。季節によっては職人の作業時間が短くなることもあるため、予定より1〜2か月余分に見ておくと安心です。
追加費用を考慮する
家づくりでは、当初の見積もりよりも最終的な費用が10〜15%程度アップすることがよくあります。なぜなら、工事請負契約から着工までの間に、設備のグレードアップや仕様変更を希望するケースが多いからです。
工事後に「システムキッチンの機能をグレードアップしたい」「収納スペースを増やしたい」といった要望は意外と出てくるものです。資金計画の段階から全体予算の10〜15%程度を予備費として確保しておくと、追加費用にも柔軟に対応できるため、満足度の高い家づくりができますよ。
優先順位をつける
予算や土地の制約から、家族の希望をすべて実現することはできないケースはよくあります。下記のように、家づくりでは何を優先するか、基準をハッキリともっておくことが重要です。
- 耐震性や耐久性などの安全性を最優先にするのか
- デザイン性やこだわりの素材を重視するのか
- コストパフォーマンスを重視するのか
「絶対に譲れないポイント」と「できれば実現したいポイント」を区別しておくことで、限られた予算のなかでも満足度の高い家づくりが可能になりますよ。
【よくある失敗】後悔事例から学ぶ家づくり
家づくりは人生で最も大きな買い物の一つです。後悔しないように進めていかなければなりません。しかし、多くの方が家づくりの過程や完成後になんらかの後悔を経験しています。ここではよくある失敗事例から、同じ轍を踏まないためのポイントを紹介します。
「【完全版】住宅購入で後悔しない!おさえておくべきポイントを解説」でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
準備・計画段階での失敗談
家づくりの準備や計画段階での失敗談を紹介します。
予算を大幅にオーバーした
家づくりでよくある失敗の一つが予算オーバーです。設備のグレードアップなどで、最終的な費用が当初の見積もりよりも10〜15%程度増加することはよくあります。失敗を避けるためには、全体予算のなかに予備費として10〜15%程度の余裕をもたせておきましょう。打合せ内容はすべて書面に残し、変更の都度「追加費用がかかるのか」を確認する習慣が大切です。
家計は年収だけでなく、家族構成やライフスタイルによって大きく異なるため、無理のない計画を心がけましょう。
選んだ土地が住みづらかった
理想の家を建てても、土地選びに失敗すると日々の生活に大きな影響を及ぼします。
- 隣家の建物で日当たりが悪い
- 周辺に生活に必要な施設がない
- 通勤・通学に不便である
- 予想外の騒音や臭いがある
上記のような後悔は、引っ越す以外に解決するのは難しくなります。
土地選びでは、時間帯や季節を変えて何度も現地を訪れることが重要です。朝昼夜それぞれの時間帯で周辺環境をチェックし、平日・休日の交通量や騒音レベルも確認しましょう。
可能であれば、雨の日にも訪れて排水状況を確認すると安心です。周辺には学校・病院・スーパーなどの生活施設が整っているか、アクセスの利便性についても確認が必要です。
土地選びで悩んでいる方は「住宅購入で住む場所選びで失敗しない!後悔しないポイントを解説」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
業者に不満がある
家づくりには長期的な関係が重要なため、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。とくに住宅会社や担当者との相性は、家づくりの満足度に大きく影響します。
よくある後悔例として、以下のようなものがあります。
- 要望が伝わらず間取りに誤解があった
- 担当者の経験不足で予算見積もりが甘かった
- 契約後に対応が悪化した
これらのトラブルは、コミュニケーション不足や業者の選定ミスが原因となっています。失敗を防ぐには、複数の会社から見積もりをもらって、比較検討をすることが大切です。施工事例や口コミに加え、建築例やオーナーの声を確認すると、具体的な情報が得られます。打合せでは視覚資料を活用し、都度確認することで誤解を防げます。
担当者との相性がどうしても合わない場合は、早めの変更や思い切って業者を変えることも検討しましょう。
設計・施工段階での失敗談
家づくりの設計や施工段階での失敗談を紹介します。
間取りに後悔している
「家事動線が悪かった」
「収納をもっとつくればよかった」
などの後悔は、よく耳にする内容です。
間取りの後悔を防ぐためにも、生活動作をシミュレーションするのがおすすめです。朝の支度から夕食の片付けまで、一日の流れを具体的に想像し動線を確認すると、理想的な間取りがわかります。
収納計画では家族全員の持ち物を把握し、床面積(約10〜15%)を収納への割り当てが目安となります。家族構成の変化を考慮し、柔軟な間取りを選ぶと長く快適に暮らせる家になりますよ。
コンセントが足りない
「必要な場所にコンセントがない」
「数が足りず延長コードだらけになった」
というのは、暮らしてみて初めて気づく内容です。
コンセント問題を解決するには、下記の対策が効果的です。
- 各部屋で使用する家電をリストアップし、配置も決める
- 準施工より2~3割増しでコンセントを設置する
- キッチンでは調理家電や小型家電の充電も考慮し、作業台付近に多めに配置する
- リビングではソファ周りや窓際、将来のレイアウト変更を想定する
コンセントは後付けが大変なので、計画段階でしっかり考えておきましょう。
完成後の失敗談
家づくりが完成した後の失敗談を紹介します。
メンテナンス費の負担が大きい
数年後に大きな負担となるのがメンテナンス費用です。外壁や屋根の塗り替え、設備の更新など、建物維持には一般的に建築費の年1%程度の費用がかかります。見た目や機能性だけで選んだ素材が、想像以上のメンテナンス負担を生むケースが少なくありません。
メンテナンス費用の失敗を避けるには、下記を意識しましょう。
- 外壁や屋根に耐久性の高い素材を選ぶ
- 将来の大規模修繕に備えて、資金計画にはメンテナンス費用を組み込む
メンテナンスや光熱費などのランニングコストは「住宅購入前に知るべきランニングコスト!6つの節約術も紹介」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
失敗せずにスムーズに家づくりを行うには住宅相談窓口がおすすめ
初めての家づくりでは迷うことがたくさんありますよね。家づくりの失敗を防ぐには、専門家のサポートが効果的です。
中立の立場で具体的なアドバイスをもらうためにも、住宅相談窓口を利用しましょう。
住宅相談窓口を利用するメリットは下記のとおりです。
- 効率的に有用な情報収集ができる
- 希望条件や優先順位を整理できる
- 資金計画を相談できる
- 自分の要望や予算にあった会社を紹介してもらえる
住宅相談窓口の利用は、近年増えてきている方法です。理想の家づくりの第一歩として、相談窓口を活用してみましょう。住宅相談窓口を知りたい方は「住宅購入で迷ったら住宅相談窓口のアドバイザーに相談しよう!」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
家づくりでよくある質問
家づくりでよくある質問を紹介します。
Q:家づくりを始めるタイミングは?
A:家づくりを始めるタイミングは、ライフイベントや経済状況によって異なります。結婚や子どもの誕生、転勤などの大きな変化がある時期は、検討するきっかけになります。住宅ローンの金利が低い時期や、政府の住宅支援制度が充実しているタイミングを狙うのも一つの方法です。
Q:工事中に変更はできる?
A:工事中の変更は可能ですが、内容によっては追加費用がかかったり、工事が長引いたりする可能性があります。変更を希望する場合は、できるだけ早く住宅会社に相談し、費用や影響を確認したうえで決断しましょう。
Q:トラブルの対処法は?
A:家づくりでは、設計の食い違いや工事の遅れ、予算超過などのトラブルが発生します。契約内容をしっかり確認し、曖昧な点は事前に質問することが重要です。
>>【事例アリ】住宅購入のトラブル!相談先や解決手順を徹底解説
まとめ
家づくりは人生で最も大きな買い物の一つであり、計画から完成まで約1年もの期間が必要です。成功の鍵は、事前の情報収集と綿密な資金計画にあります。予算には必ず余裕をもたせ、追加費用に備えましょう。
土地選びでは周辺環境や日当たり、法的規制を専門家に相談することが重要です。住宅会社選びは、実績や対応力を比較し、相性の良いパートナーを選びましょう。設計段階では家族の優先順位を明確にし、ライフスタイルの変化も考慮した間取りにすると後悔が防げます。
相談窓口やプロの力を借りれば、効率的に理想の家づくりを進められます。おうちの買い方相談室では、初めての家づくりの方にわかりやすくアドバイスをしているので、家づくりに少しでも不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。わたしたちとともに、各ステップのポイントをおさえ、理想の家づくりを目指しましょう。