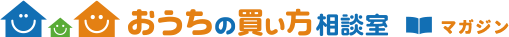【事例アリ】住宅購入のトラブル!相談先や解決手順を徹底解説

憧れのマイホームを手に入れたものの、購入後に欠陥がみつかるなど「思わぬトラブル」に見舞われるケースもあります。住宅購入は一世一代の買い物なのに、トラブルで時間やお金、幸せな気持ちまで奪われるのは誰だって避けたいものですよね。住宅の購入トラブルを未然に防ぐには、「傾向と対策」を事前に把握しておくことが重要です。またトラブルが万が一発生してしまっても、不利益を被らないように「しかるべき手続きや手順」や「相談先」を押さえておくことが肝心です。
この記事では、よくある住宅購入トラブルのパターンやその対策、さらにトラブルが起きた際に相談先などをご紹介します。「しっかり備えて、安心して夢のマイホームを手に入れたい!」というあなたの強い味方となる必見の内容が満載です。ぜひ最後までお読みください。
住宅購入の契約トラブルと対処法
住宅購入の契約でトラブルになりやすいのは、下記の3つの内容です。
- 契約内容の誤解
- 契約内容との相違や瑕疵による契約不適合
- 契約解除
詳しく解説します。
契約内容の誤解
住宅購入に関する契約書は専門用語が多く内容が複雑なため、契約内容を誤解してしまうケースも多いです。たとえば住宅ローンを利用して物件を購入する際、売買契約書に「ローン特約」が付いていない点に気づかず、契約解除の際に手付金を放棄しなければならなくなった事例があります。
契約内容を誤解しないためには、わからない点を曖昧にせず、事前に確認する姿勢が重要です。
契約内容との相違や瑕疵による契約不適合
住宅を購入した際によくあるのが、契約内容との相違や瑕疵(欠陥・不備)による「契約不適合」のトラブルです。
契約不適合にあたるのは、下記のようなケースです。
- 建物の構造や設備が契約内容と異なる
- 建物の品質に問題がある
- 建物の面積が契約書と異なる
契約不適合の場合は、買主は売主に対して以下のいずれかで請求できます。契約不適合をみつけたら、契約書にある期間内に必ず請求するようにしましょう。
| 履行の追完請求 | 不適合部分を完全な状態(交換・補修するよう)に請求する権利 |
| 代金減額請求 | 契約価格を減額するよう請求する権利 |
| 損害賠償請求 | 不適合によって生じた損害に対する賠償を請求する権利 |
| 契約の解除 | 契約不適合が重大な場合、契約を解除する権利 |
契約解除
契約解除はできるかぎり避けたいところですが、契約解除せざるを得ない状況になる可能性は否定できません。
契約する際は、契約解除の内容もしっかり確認するようにしてください。
- 手付金は戻ってくるのか
- そもそも、契約解除できるかどうか
購入者都合で契約解除を行う場合、手付金は戻ってこないのが一般的です。また契約履行に着手したにもかかわらず一方的な理由で契約を解除する場合は、手付金を放棄したとしても、さらに違約金などの損害賠償を求められるでしょう。
契約解除は信頼関係が崩れやすいため、トラブルになる可能性も高いです。契約解除を避けるためにも条件は事前に細部まで確認しておき、リスクを最小限に抑えるようにしましょう。
住宅ローン特約は重要
住宅ローン特約は、ローン審査が通らなかった場合に契約解除するための重要な条項です。内容を正しく理解しないとトラブルの原因になるため、注意しましょう。
住宅ローン特約には「解除条件型」と「解除権留保型」の2種類があります。気を付けなければならないのは、解除権留保型は売主に契約解除の意思を期限内に伝える必要がある点です。解除権留保型を選択した場合には、契約解除ができなくなる前に必ず通告するようにしましょう。
注文住宅でよくあるトラブル事例
下記は、注文住宅でよくあるトラブルです。
- 引き渡しが遅れた
- 施工ミスがあった
- 追加費用が発生した
- 出来上がりがイメージと違った
入居までにたくさんのステップをふまなければならない注文住宅は、特にトラブルが起きやすいです。それぞれを詳しく見ていきましょう。
引き渡しが遅れた
注文住宅でよくあるのが、工期の遅れで引き渡しが間に合わずトラブルになるケースです。遅延の原因は、天候や資材の納期遅れ、人員不足など様々ですが、変更や追加工事が工期を延ばしてしまう場合も多いです。
引っ越し日がずれてしまうと、仮住まいの家賃が余計にかかるうえ、家具の搬入や転居のための手続きを見直す手間もかかります。さらに、子供が転校するタイミングがずれるなど、家庭内の精神的負担も避けられません。家づくりを計画的に進めるためにも、工事中にできるだけ変更がないよう、プランや仕様は定められた期間までにきっちり固めておきましょう。
なお、工事遅延の原因が「発注ミス」など、施工会社側に明らかに非がある場合は、遅延に対して補償してもらえる可能性が高いです。契約を交わすときは、遅延した場合の取り決めも確認しておくと安心ですよ。
施工ミスがあった
施主の要望に合わせて建物を仕上げていく注文住宅では、職人の経験不足・図面への記載ミス・コミュニケーション不足・現場の確認不足などが理由で、施工ミスが起こりやすいです。
施工ミスは「簡単に手直しできるもの」と「できないもの」に分かれます。たとえば、予定とは違った壁紙が貼られているケースは手直しが簡単ですが、配管の施工ミスなどは仕上げ材を解体してからやり直さなくてはならないため工期は長引きます。
住宅会社は細心の注意を払って施工しなければなりませんが、人がする仕事なので施工ミスが起きてしまう可能性は否定できません。施工ミスをできるかぎり防ぐためにも、施主として工事中も厳しい視点で現場をチェックするようにしてください。
追加費用が発生した
注文住宅では、契約後の予期せぬ問題で「予定外の費用」がかかるケースが多いので、注意が必要です。
契約前に追加費用のリスクについて詳細な説明を受けたとしても、追加費用の金額を契約時点で完全に予測できません。たとえば地盤調査などで大規模な地盤改良が必要だと分かった場合は、追加費用が100万円を超えてしまうケースもあります。資金計画では、追加費用を見込んで「総予算の10〜20%」を目安に余裕を持たせておくことが肝心です。
出来上がりがイメージと違った
注文住宅では、完成後に「思っていたものと違う!」とトラブルになるケースがあります。これは、施工ミスはなくても、情報の食い違いやイメージの共有不足などが原因です。
注文住宅の家づくりは、実際の建物がまだ存在していない中、図面で想像しながら打ち合わせをしていく必要があります。実物がないため、住宅会社と施主間の認識がずれていても気づかない場合も多いです。
完成後のイメージは模型やCGを活用してできるだけ具体化するのが大切です。何度も打ち合わせを重ねて双方でイメージを共有しておきましょう。
建売住宅でよくあるトラブル事例
建売住宅でトラブルが多いのは、下記の3つです。
- 施工不良があった
- 点検口がなかった
- アフターサービスが手厚くなかった
すでに完成している建売住宅は、仕上がりを確認してから購入できるため一見トラブルがなさそうですが、トラブルになるケースもあるので注意しましょう。
施工不良があった
建売住宅で最も多いトラブルの一つが施工不良です。壁のひび割れや配管の不具合などのトラブルは、暮らしてから初めて気づく場合も多いです。
後悔しないためには、物件や販売会社の見極めが肝心です。建売住宅はスピード重視で建設されることが多いため、細部の確認が不十分な傾向があると言われがちですが、もちろん良い建売住宅もたくさんあるので安心してください。
建売住宅の見極めは「新築の建売住宅を購入する時の流れや注意点を解説」の記事で解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
点検口がなかった
建売住宅でありがちなのが、必要な場所に点検口が設置されていないケースです。点検口がなければ給排水管や電気配線の確認や修理が難しいため、いざというときは壁の解体・復旧が必要になる可能性もあります。
点検口は購入時には意識しないため、メンテナンスが必要になった数年後にはじめて、点検口がないことに気づく場合も多いです。将来的なメンテナンスに支障をきたさないためにも、点検口の有無だけでなく、位置や数も必ずチェックするようにしてください。
アフターサービスが手厚くなかった
暮らした後で、「思うようなアフターサービスは受けられない・・・」と後悔するケースがあります。建売住宅を購入する際は、金額や物件ばかりに目がいき、アフターサービスまでは考えが及ばない場合も多いです。
基本的に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」については、法律によって10年保証がありますが、それ以外の部分については会社独自の保証が採用されます。当然あると思っていたアフターサービスの内容がついていない場合もあるので、契約前に必ず確認しておきましょう。
中古住宅でよくあるトラブル事例
中古住宅の購入でよくあるのは、下記のような物件の瑕疵です。
- シロアリ被害が発覚した
- 雨漏りや水漏れが見つかった
- 設備機器が故障した
詳しく解説します。
シロアリ被害が発覚した
中古住宅を購入した後、シロアリ被害が発覚してトラブルになるケースは多いです。
しかし、法律では「契約不適合責任」が定められています。シロアリ被害を購入前に知らされていなかった場合は、原則1年以内なら売主に費用を負担してもらえます。また、売主がシロアリ被害を事前に把握していなかった場合でも、期間内であれば基本的に契約不適合責任が適用される可能性は高いです。
雨漏りや水漏れが見つかった
屋根や外壁、配管の劣化が進んでいる中古住宅では、購入後に雨漏りや水漏れが見つかるケースもあります。雨漏りや水漏れがあっても、契約不適合責任が適用されれば売主側に修繕費用を負担してもらえます。
しかし中古住宅の場合は、基本的に「ある程度の経年劣化はやむを得えない」とされています。新築物件よりも契約不適合の判断基準が緩和されるため、状況によっては契約不適合責任が適用されずに修繕費用が買主側の負担となるケースもあるので注意しましょう。
なお個人間での売買では、契約不適合責任の期間を短縮する特約や責任を負わない特約が設けられている場合も多いです。購入前には、物件の状態や契約内容をきちんと把握しておくことが肝心です。
設備機器が故障した
中古住宅を購入したものの、入居後すぐに設備が故障してしまうケースがあります。「給湯器のお湯がでない」「ガスコンロが作動しない」など、設備機器が壊れると生活に支障をきたすため交換せざるをえませんよね。
しかし、一般的な契約では、引き渡し後1週間以内に発見されたもののみが売主の負担となり、期間をすぎると買主負担になります。保証の起算日を「引き渡し日ではなく「入居日」と勘違いし、保証期間をすぎてしまう人も多いので注意しましょう。
中古住宅の引き渡しを受けたら、まずは設備機器が作動するか確認するようにしてくださいね。
住宅購入のトラブルを防ぐ5つのポイント
住宅購入のトラブルを未然に防ぐためにも、下記の5つをおさえておきましょう。トラブルにあう確率をぐっと減らせます。
- 住宅相談窓口を利用する
- 信頼できる業者を選定する
- 契約内容や重要事項説明書を確認・精査する
- ホームインスペクションを利用する
- 現場を確認する
詳しく解説します。
住宅相談窓口を利用する
トラブルを未然に防ぎたいなら、住宅購入専門のプロが在籍する「住宅相談窓口」の利用がおすすめです。なぜなら、相談窓口を利用すれば中立的な立場から客観的なアドバイスを得られるため、自分自身では気づかなかった潜在的な問題点も浮き彫りになるからです。
住宅相談窓口は無料なので、住宅購入を検討し始めた段階で気軽に利用するとよいでしょう。将来的なトラブルのリスクを大幅に軽減できるため、安心して住宅購入を進めていけますよ。
住宅相談窓口を利用するメリット・デメリットは「住宅購入で迷ったら住宅相談窓口のアドバイザーに相談しよう!」で解説しています。記事では、住宅相談窓口6社の特徴も徹底比較しているので、あなたにぴったりの相談先もわかります。ぜひ参考にしてください。
信頼できる業者を選定する
信頼できる業者を選べるかどうかは、住宅購入の成功を左右する重要な要素です。信頼できる業者を選ぶためにも、以下のポイントを重視するようにしてください。
- 複数の業者に相談する
一つの業者だけに頼らず、複数の業者に見積もりを依頼する。
- 口コミや評判を調べる
口コミや評判をインターネットなどで調べる。
- 会社の規模や実績
経営状態が安定しているか、豊富な実績が良いかどうかなどを調べる。
- 担当者の対応
担当者の対応は丁寧か、疑問に思うことを何でも聞けるかどうかを確認。
良い業者であれば、契約内容が明白で分かりやすいのでトラブルになりにくいです。コミュニケーションも円滑で施工品質も高いので、気持ちよく住宅購入を進めていけますよ。妥協せず、良い業者を見つける努力を惜しまないようにしてくださいね。
契約内容や重要事項説明書を確認・精査する
トラブルを回避するためにも、契約内容は細部まで確認しておきましょう。
不明瞭な条項は、後々トラブルになりかねません。契約内容を曖昧に把握していると、期待していた工事やサービスが提供されない可能性があります。専門用語や難しい内容など、わからない点は必ず担当者に質問して理解しておいてくださいね。
契約書や重要事項説明書は、特に下記の内容をチェックしておきましょう。
- 代金と支払い方法
- 床面積や敷地面積
- 登記関連
- 電気・ガスなどのインフラ整備
- 引渡し日や今後の流れ
- キャンセル条件や違約金の額
- 契約不適合責任の履行に関する措置
- 引っ越し前の物件に損害があった場合の対応
- 中古物件の場合は付帯設備の取り扱い
- 住宅ローンの契約時
住宅購入の契約書や重要事項説明書の注意点は、「【重要】住宅購入での売買契約での注意点を解説!」で解説しています。自信を持って契約書にサインするためにも、ぜひ参考にしてください。
ホームインスペクションを利用する
ホームインスペクションを利用すれば、購入前に住宅の状態を把握できるため、不具合があっても早い段階で発見できます。
物件購入後に不具合が見つかると修繕費用が予想外にかかってしまうケースも多いです。しかし、ホームインスペクションを利用すれば修繕リスクを軽減できるうえ、将来の修繕費用まで見積もりやすくなります。さらに、結果を購入時の価格交渉にも活用できるため、適正金額での購入が期待できます。
ホームインスペクションは、トラブルを回避するだけでなく物件の価値と価格の適正性を判断するためにも重要です。費用は10万円程度かかりますが、ホームインスペクションを利用するメリットは大きいです。中古住宅を購入する際は、ぜひ検討してみてくださいね。
現場を確認する
注文住宅なら、工事中は頻繁に現場に出向くようにしましょう。
施工ミスや手抜き工事、使用される建材などは、完成後では気づきにくいものです。そのため、現場に行って進捗状況を確認したり、材料や施工品質をチェックすることは、トラブル防止につながります。
完成後は工事写真をもらえますが、万が一を考えて自分自身でも工事中の状況を撮影しておくのがおすすめです。職人や施工会社に、より気を引き締めてもらう意味でも、細部まで目を配っている姿勢をアピールしておくとよいでしょう。
トラブルの解決手段
トラブルの解決手段は主に3つあります。解決は、以下の順序で試みるのが一般的です。
- 話し合い
- 紛争解決手続き
- 裁判
話し合いは、当事者間での直接交渉が最初のステップです。最も迅速かつ低コストな解決方法です。話し合いで解決しない場合、裁判外での紛争解決手続を利用できます。費用は申請手数料の1万円程度ですが、法律上での効力をもつうえ裁判と比べて迅速な解決も可能です。
しかし、話し合いや紛争解決手続で解決できないケースもあります。その場合は、最終的に裁判所での訴訟となります。
トラブル発生時の対応方法と手順
トラブルが発覚したら、下記の手順で対応しましょう。
- 状況を正確に把握する
- 相手方に連絡する
- 専門家へ相談する
それぞれを詳しく解説します。
状況を正確に把握する
まずは、状況を正確に把握することが重要です。問題点を明確にするために、以下の方法で事実を整理しましょう。
- 契約書や見積書を再度見直し、契約内容を確認する
- 写真・議事録・メールでのやりとりなど、トラブルの証拠を収集する
状況を具体的に整理すれば、次の交渉や専門家への相談がスムーズになります。また、問題の全体像を把握することで、冷静に対処のための準備を整えられます。
相手方に連絡する
次に、住宅会社や不動産会社に連絡します。冷静かつ具体的に状況を伝えて、改善を求めましょう。連絡する際は、感情的にならないよう注意し、証拠を提示しながら事実を伝えるようにしてください。
対応してもらえない場合や返答が遅い場合は、再度連絡する際に記録を残すようにしておくと、後から証拠として残るため安心です。内容証明郵便やメールなど、履歴が残る方法の活用もおすすめですよ。
専門家へ相談する
解決が難しそうな場合は、早めに専門家へ相談するようにしてください。国民生活センターや法テラスへの相談は無料でできますが、弁護士からのアドバイスはもちろん有料です。ですが、トラブルの内容によっては弁護士を通したほうが、問題を早期に解決でき不利益を大きく軽減できる場合もあります。
【保存版】トラブルが起こった際の相談先5選
住宅購入によるトラブルの相談先は、以下の5つが一般的です。
- 住まいるダイヤル
- 国民生活センター
- 法テラス
- 首都圏不動産公正取引協議会
- 弁護士
それぞれに特徴があるため、トラブル内容に合わせて相談先を選ぶことが肝心です。
住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

出典:住まいるダイヤル
住まいるダイヤルは、住宅専門の相談窓口として国土交通大臣から指定を受けた機関です。
技術的な問題から法律的な問題まで幅広い相談に対応しており、弁護士や建築士などの専門家にも必要に応じて相談できます。また、各都道府県にある「住宅紛争審査会」への紛争解決手続きも可能です。
| 住まいるダイヤル
電話番号:0570-016-100(ナビダイヤル) 受付時間:平日10~17時(祝休日、年末年始を除く) |
【相談内容の例】
- 住宅の欠陥や不具合
- 業者が補修依頼に対応してくれない
国民生活センター(消費者ホットライン)

出典:国民生活センター
全国各地にある国民生活センターは、消費者のさまざまな相談に対応しています。初期相談に適しているのが特徴で、必要に応じて最適な専門機関も紹介してくれます。
| 国民生活センター
電話番号:188(局番なし) 受付日時:相談できる曜日・時間帯は相談窓口により異なります。原則毎日利用可能(年末年始を除く) |
【相談内容の例】
- 住宅の欠陥や不具合
- 業者との金銭トラブル
法テラス

出典:法テラス
法テラスは、法的トラブルの解決案内所として国が運営する公的機関です。住宅購入の法的なトラブルも無料で相談できます。
| 法テラス
電話番号:0570-078374 受付日時:平日9~21時、土曜9~17時(日曜・祝日は除く) |
【相談内容の例】
- 解約や契約内容違反などの法律相談
- 近隣トラブル
首都圏不動産公正取引協議会

首都圏不動産公正取引協議会は、不動産広告の適正化を推進する重要な自主規制団体です。広告内容に関するトラブルであれば相談できます。
| 首都圏不動産公正取引協議会
電話番号:03-3261-3811 受付日時:平日10~16時 |
【相談内容の例】
- 広告内容との相違
- 過大な宣伝
弁護士
損害賠償や返金請求を検討する場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。トラブルの問題点(弱点)や対応方針を明示してくれますし、交渉や裁判で代理人を務めてくれます。
【相談内容の例】
- 権利関係のトラブル
- 売買契約書のチェック
- 法令違反の疑い
まとめ
この記事では、よくある住宅購入トラブルのパターンやその対策、さらにトラブルが起きた際の相談先を紹介しました。信頼できる業者を見極め、契約内容をしっかり確認すれば、多くのトラブルは未然に防げます。万が一トラブルになっても、知識があれば迅速に対応できるので大きな問題へ発展しにくいですし、不利益も被らなくてすむでしょう。
住宅購入は事前の準備が「成功の鍵」となります。住宅の購入を検討し始めたら、まずは無料で利用できる「住宅相談窓口」に相談してみてください。プロからのアドバイスを参考に、トラブルを回避しながら着実に購入を進められますよ。マイホーム購入の夢を叶えるために、慎重かつ冷静に準備を進めましょう。