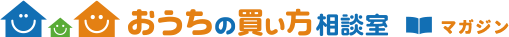住宅購入の諸費用とは?内訳と購入時の注意点・ポイントについて解説
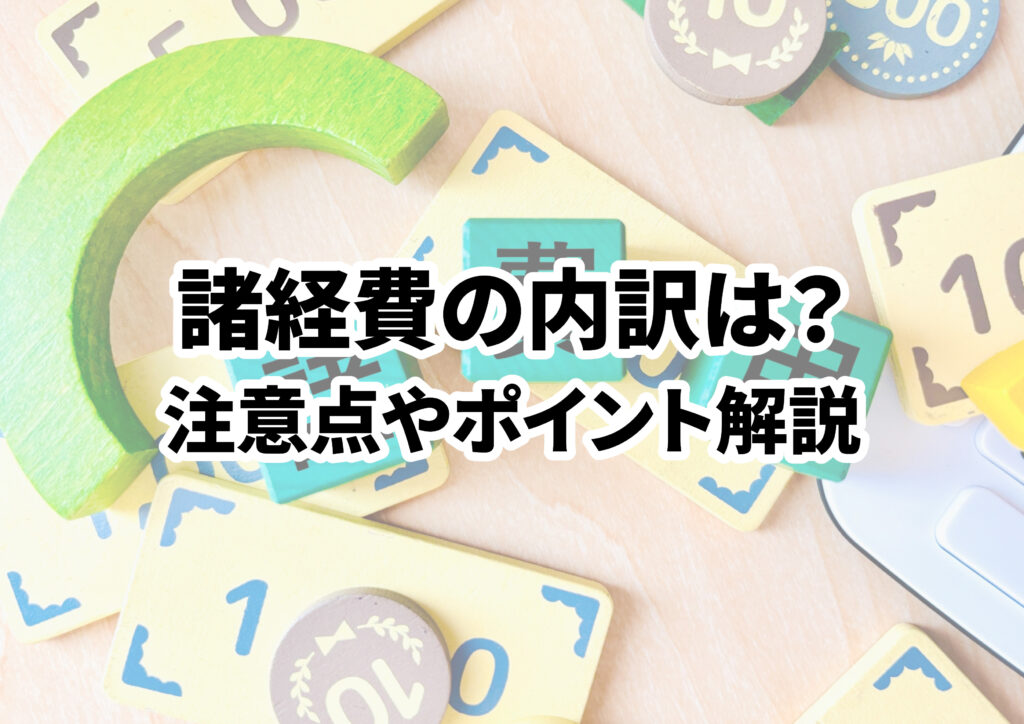
マイホームを購入する時、建物本体価格だけを見て予算を検討していませんか?実は、住宅購入にかかる費用は本体価格だけではなく、「諸費用」というものがかかります。
「諸費用って何?」
「どのくらいの金額が必要なの?」
初めて住宅購入する方にとって、そんな疑問や不安を抱く方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、住宅購入にかかる諸費用とは何か、内訳や諸費用に関する注意点、住宅購入時にかかる意外な出費について徹底解説します。住宅購入を検討されている方は、資金計画のためにも諸費用についてしっかりと学んでいきましょう。
住宅購入に必要な諸費用(諸経費)とは?
住宅購入には、建物本体価格の他に「諸費用(諸経費)」がかかります。諸費用とは、住宅購入時にかかる税金や手数料のことです。諸費用は通常、住宅ローンの借入額には含まれないため、基本的には現金で支払わなければなりません。
目安としては、新築物件なら物件価格の3〜7%、中古物件なら物件価格の6〜10%の諸費用がかかってきます。
ここでは、以下の4つに分類し、それぞれにかかる諸費用とその内訳を解説していきます。
- 物件にかかる諸費用
- 住宅ローンにかかる諸費用
- 保険にかかる諸経費
- その他の諸費用とその内訳
ではさっそく見ていきましょう。
物件にかかる諸費用
物件にかかる諸費用には以下のようなものがあります。
- 印紙税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 固定資産税精算金・都市計画税精算金
- 修繕積立基金
- 仲介手数料
それぞれの諸費用に関して、項目別に説明していきます。
印紙税
印紙税とは、住宅を購入するときに交わす契約書に貼る印紙代のことです。契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑に割印を押すことで納税したことが記されます。
住宅を購入するときに交わす契約書には、以下の3つがありますが、それぞれに印紙税がかかります。
- 売買契約書(土地や建物を売買するときの不動産譲渡契約書)
- 建設工事請負契約書(注文住宅を建てるときの契約書)
印紙税額は、下記のように契約金額によって必要な金額が変動します。不動産売買契約・建設工事請負契約を交わす際、租税特別措置法により、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書について印紙税の軽減措置が適用されます。
| 記載された契約金額 | 印紙代(不動産売買契約・建設工事請負契約※軽減税率) |
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 400円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
上記のように、契約金額によって必要になる印紙代が変わってくるため、事前に確認しておくようにしましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した時に課税する地方税です。不動産取得税は、「固定資産税評価額」で算出されます。不動産取得税の税率は、不動産の種類に問わず「固定資産税評価額の4%」が基本です。ただし、令和9年3月31日までは、特例として土地及び住宅を取得した際にかかる税率は「固定資産税評価額の3%」になります。
登録免許税
登録免許税とは、取得した不動産を自分の所有物であることを登記簿に記録する際にかかる税金です。登記の種類には、所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記などがあります。登録免許税で負担する税額について、以下にまとめてみました。
【土地の所有権移転登記】
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
| 売買 | 固定資産税評価額 | 20/1,000 | 令和8年3月31日までに陶器を受ける場合は、15/1,000が適用される。 |
| 相続、法人の合併または共有物の分割 | 固定資産税評価額 | 4/1,000 | |
| その他 | 固定資産税評価額 | 20/1,000 |
【建物の所有権移転登記】
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
| 所有権の保存 | 固定資産税評価額 | 4/1,000 | 個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照。 |
| 売買または競売による所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 20/1,000 |
【建物の所有権移転登記】
| 内容 | 内容 | 税率 | 軽減税率 |
| 住宅用家屋の所有権の保存登記 | 個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1.5/1,000 | 登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要がある。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられない。 |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記 | 個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 3/1,000 | 同上 |
| 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 | 個人が、令和9年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 1/1,000 | 同上 |
| 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 | 令和9年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 1/1,000 | 同上 |
上記のように、それぞれどのように住宅を取得したかによって税率が変わってきます。
司法書士への報酬
住宅購入時に登記簿に記録する際に、司法書士に手続き代行を依頼した場合、司法書士へ報酬を支払わなければなりません。報酬金額は、登記の種類や依頼する司法書士によって異なりますが、大体1万円〜13万円前後かかるとされています。
固定資産税精算金・都市計画税精算金
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している場合に負担する税金です。年の途中に不動産の引き渡しがあった場合、所有権が移動してから12月31日までの期間の税金を支払わなければなりません。これを固定資産税精算金・都市計画税精算金といいます。固定資産税と都市計画税は以下の計算方法で算出されます。
| 固定資産税評価額×税率(1.4%)の日割り金額 |
こちらも登録免許税や不動産取得税と同様、条件を満たすことで税額軽減措置が適用されます。
修繕積立基金
修繕積立基金とは、新築マンションの引き渡し時にかかるお金です。物件の引き渡し時に支払うことが一般的で、金額は購入するマンションによってことなります。場合によっては数十万円支払わなければならないこともあるため、新築マンション購入の際は金額を確かめておきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社が売買を仲介する物件を購入した場合にかかる手数料です。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で決まっており以下のように購入金額によって異なります。
| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円〜400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
住宅ローンにかかる諸費用
続いて、住宅ローンにかかる諸費用には以下のようなものがあります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 融資事務手数料
- ローン保証料
- 物件調査手数料
それぞれの諸費用に関して、項目別に説明していきます。
印紙税
住宅ローン契約書(金銭消費賃借契約書)を交わす際にも印紙代を負担しなければなりません。負担する印紙代は、売買契約等と同様に契約金額によって以下のように変わってきます。
| 記載された契約金額 | 金銭消費賃借契約書 |
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 400円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
登録免許税
住宅ローンの借入時にも登録免許税が発生します。なぜなら、金融機関が土地や建物に抵当権を設定する際に登記をしなければならないためです。
| 内容 | 内容 | 税率 | 軽減税率 |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋の新築または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1/1,000 | 同上 |
司法書士への報酬
物件にかかる諸費用と同じく、登録免許税の登記の際に司法書士に手続きを依頼する場合に司法書士に支払う報酬のことです。支払う金額は4万〜8万円前後が大体の目安となります。
融資事務手数料
融資事務手数料とは、住宅ローンの契約時に金融機関に支払う諸費用のことです。融資実行の際の手続きに対する事務手続き費用になります。目安は大体「借入金額×2.2%」程度です。
ローン保証料
ローン保証料とは、住宅ローンを借りる際に保証会社と保証契約をする際にかかる費用です。保証契約を締結することで、返済途中に止むを得ない理由で返済ができなくなった時に債務者に代わって保証会社が一括返済してもらえます。これは、保証会社と債務者の間で保証契約を締結しなければ、金融機関から融資してもらうことはできません。ローン保証料の目安は、借入額の大体0.8〜2.2%程度で、金融機関によって異なります。
物件調査手数料
物件調査手数料とは、購入予定の住宅が住宅ローンの融資を受ける基準に適合しているかどうかを調査する手数料のことです。金額の目安は以下の通りになります。
- 一戸建て:6〜8万円程度
- マンション:4〜6万円程度
上記に加え発行手数料もかかります。
保険にかかる諸経費
住宅購入の際に加入する保険をまとめてみました。
| 保険名 | 内容 |
| 団体信用生命保険 | 契約者が万が一亡くなったり、所定の高度障害になったりしたときに、保険金から住宅ローンを返済してもらえる保険。 |
| 火災保険 | 住宅や家財に生じた損害を補償してくれる保険。 |
| 地震保険 | 火災保険では賄えない地震による損害をカバーしてくれる保険。 |
| 医療保険 | 病気や怪我によって働けなくなった時に補償してくれる保険。 |
| 収入保障保険 | 万が一契約者がなくなった時に年金形式でお金を負担してくれる保険。 |
上記のうち、団体信用生命保険は住宅ローンを借りるために加入を求められることが多いです。
その他の諸費用とその内訳
住宅購入時には、その他にも以下のように負担しなけれならない諸費用が発生します。
| 諸費用 | 内容 |
| 水道負担金 | 一戸建てを購入する場合など、新たに水道を利用する際に必要。 |
| 引っ越し費用 | 現在の住まいから新居に引っ越す際に発生する費用。仮住まいが必要な場合、仮住まいでの家賃も発生する。 |
| 家具購入費用 | 新居に必要な家電や家具の購入費用。 |
上記のように、これまで説明したものとは別で負担する費用があるため、どのくらいの費用が必要になるのかを確かめなければなりません。
物件購入での諸費用の注意点
物件購入で諸費用がかかることは理解いただけたかと思います。これまで紹介した内容を踏まえ、物件購入での諸費用の注意点を解説していきます。
不動産仲介手数料の計算
先に説明したように、不動産仲介手数料は以下のように上限が決まっています。
| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円〜400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
上記の計算式に当てはめることで、不動産購入時にかかる仲介手数料を算出できます。
売買の金額が高くなるほど上限額が高額になります。
例えば、不動産の売買価格が1,000万円の場合、以下の通りに仲介手数料が算出されます。
| 1,000万円×3%+6万円=36万円
36万円×10%(消費税)=39万6,000円 仲介手数料/39万6,000円 |
仲介手数料の上限を簡単に計算できるので、資金計画の際の参考に利用しましょう。
登記費用とは?必要な手続きの詳細
登記費用は、不動産取得の際に登記する際に発生する登録免許税や手数料、司法書士への報酬などのことです。
住宅を購入したら、所有権がご自分に移ったことを示すために「所有権の移転登記」をしなければなりません。建物を新築した場合や登記されていない建物を購入した場合には、「建物の表題登記」と「所有権の保存登記」というものが必要になります。上記の登記には専門的な知識が必要になることから、司法書士に依頼して代行してもらうことが多いです。
住宅ローンで知っておきたいポイント
住宅ローンでも必要になる諸費用があります。ここでは、住宅ローンの際に知っておきたい節約術や交渉ポイントについてご紹介します。
事務手数料の相場と交渉ポイント
先ほども紹介したように、住宅ローンの事務手数料の相場は、目安は大体「借入金額×2.2%」程度です。
実は住宅ローンの融資事務手数料は、交渉次第で安くできる可能性があります。それは、交渉する際に、「別の金融機関でもローンの相談をしている」ことを伝えることです。これにより、顧客を逃したくない金融機関の担当者は、事務手数料を無料にすることで顧客に契約を促すことができます。
ただ、住宅ローンの同時申し込みをする際、3〜4社などたくさんの金融機関に同じタイミングで申し込むと、「形振り構わず申し込んでいるのでは?」と不審がられる恐れがあります。ネガティブなイメージを相手に与えないためにもせめて2社程度に止めて交渉するようにしましょう。
ローン保証料の計算方法と節約術
こちらも先ほど解説したように、ローン保証料の目安は、借入額の大体0.8〜2.2%程度です。また、返済期間に応じて保証料も変わってきます。ローン保証料には、「一括前払い型(外枠方式)」と「金利上乗せ型(内枠方式)」の2種類の支払い方法があります。
一括前払い型なら、保証料に利息がつかないため、支払い総額が抑えられます。また住宅ローンの繰上げ返済をした場合、支払った保証料の一部が返済される点もメリットです。ただし、契約時に一括で支払いが必要なので、まとまった資金が必要です。
金利上乗せ型は、月々の住宅ローンの適用金利にさらに金利を0.2%程度上乗せして支払う方法なので、保証料の支払い総額が大きくなります。ただし契約時の諸費用の金額を抑えられるのがメリットです。
例えば、3,000万円の借入で、借入金利0.6%、返済期間35年の場合、それぞれ以下のローン保証料(2%の場合)がかかります。
| 借入金利 | 総返済額 | 借入時に支払うローン保証料 | 合計 | |
| 保証料外枠方式 | 0.625% | 3,340万8,346円 | 61万8,420円 | 3,402万6,766円 |
| 保証料内枠方式(金利+0.2%の場合) | 0.825% | 3,354万9,392円 | 0円(月々のローン支払いに組み込まれるため) | 3,354万9,392円 |
外枠方式を選択することにより、35年間で52万2,626円お得になります。ローン保証料を節約するなら、ローン借入時に一括で支払うことをおすすめします。
金融機関によっては、「保証料無料」を謳っているところもあります。しかし、保証料無料の代わりに事務手数料の負担が大きくなっていることが多いです。そのため、負担する金額は保証料がある場合とあまり変わりません。
他にもローン保証料を節約する方法があります。それは、住宅購入時に支払う頭金を増やす方法です。頭金を増やすことでローン借入金額が減るためそれに比例してローン保証料も減らすことができます。少しでもローン保証料を減らしたい方は、資金計画を行なって頭金を増やすことも検討しましょう。
火災保険や地震保険の重要性と選び方
住宅購入時には火災保険や地震保険に任意で加入します。しかし、火災保険と地震保険のどちらも加入すると年間で10万円前後負担しなければなりません。
たくさんの諸費用がかかる中でのこの負担は大きいと感じるかもしれませんが、火災保険と地震保険に加入することは、万が一の自然災害時に非常に役立ちます。
火災保険と地震保険の重要性
まず、火災保険は火事で住宅や家財が全焼したり、台風で水災や風災の被害を受けた時に生活を立て直す際に経済的負担を軽くしてくれます。火災保険に加入することで火災や落雷などのさまざまなリスクに備えられます。
火災保険では地震における被害を十分に補償してもらえない可能性があります。また、噴火や津波などによって生じた損害も保証されないことが多いです。これらの損害を補償してもらうためにも地震保険の加入をおすすめします。特に日本は地震の多い国なので、これまでにご自分が住む地域で大きな地震があったなどの事例があれば、保険料を支払ってでも保証をつけておくことが望ましいです。
火災保険と地震保険の選び方
まず、火災保険を選ぶときは、以下の5つのポイントに注目して選びましょう。
- 補償対象を決める
- 建物の構造級別(建物の種類(木造や鉄骨造など)は何か、建物の性能(耐火建築物や準耐火建築物など)は何か)を確認する
- 補償の範囲を決める
- 保険金額を決める
- 保険期間を決める
そして最後に地震保険に加入するかどうかを検討しましょう。地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険とのセット契約になります。また、住宅購入時に加入しなくても火災保険契約期間の途中でも加入することは可能です。
金利変動とその影響
住宅ローンでは固定金利と変動金利があります。変動金利の場合、半年ごとの金利の見直しによって金利が代わり、月々の住宅ローンの返済金額も変わってきます。変動金利型の住宅ローンは、固定金利型の住宅ローンよりも金利が低いです。しかし、金利が変動するたびに毎月の返済額が変動するため、返済計画が組みにくいというデメリットもあります。
今後金利が上がるとローン返済額が増えることになるため、金利上昇に備えて繰上げ返済で早めに完済するなどの対策を施さなければなりません。
購入手続きに伴う意外な費用
住宅購入手続きにはさまざまな費用が発生しますが、中には意外な出費もあります。
印紙代の基礎知識と準備方法
先にも述べたように、印紙代は契約金額によって変動します。
| 記載された契約金額 | 印紙代(不動産売買契約・建設工事請負契約※軽減税率) | 印紙代(金銭消費賃借契約書) |
| 10万円超50万円以下 | 200円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 400円 | 400円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 6万円 |
印紙を準備する場合、コンビニや郵便局・法務局・役所などで購入できます。ただし、コンビニでは一般的に200円の印紙が得られており、これより大きい額面や200円を下回る収入印紙は通常取り扱われておりません。また、コンビニでも個人経営店や駅構内のコンビニだと取り扱っていないこともあるため、郵便局や法務局・役所で購入することをおすすめします。
各種証明書の取得費用と手続き
住宅購入時には以下のような証明書の取得が必要な場合があります。
| 書類名 | 内容 | 取得費用 |
| 源泉徴収票、確定申告書、決算報告書など | 住宅ローン事前審査時に提出する収入がわかる証明書類 | 無料 |
| 物件概要署、間取り図、公図など | 住宅ローン事前審査時に提出する購入がわかる証明書類 | 無料(公図は法務局で取得、1通450円、オンラインなら430円) |
| 住民票 | 住宅ローン申込時に必要な書類、同居家族全員の続柄がわかるもの。 | 自治体によって手数料は異なる。 |
| 印鑑証明書 | 住宅ローン申込時に必要な書類。借入本人、連帯保証人、担保提供者それぞれ必要。 | 自治体によって手数料は異なる。 |
必要な証明書の手配も忘れないようにしましょう。
引っ越し費用の項目と節約テクニック
引っ越し費用と一言で言っても、以下のようにさまざまな費用がかかります。
- 引っ越し業者に依頼する費用
- 現在の住まいの退去費用
- 不用品の処分費用
- 家具・家電購入費用
引っ越し費用を節約するテクニックとして使えるものを表にまとめてみました。
| 引っ越し日時を割安な色にする | 繁忙期(3〜4月ごろ)を避けた日程にする。 |
| 不用品の処分を買取業者に依頼する | 売れそうなものがあれば売る。値段がつけられないものでも無料で回収してもらえる場合がある。 |
| 新居の家具はアウトレットで購入する | アウトレット品なら格安で購入できる可能性が高い。 |
| 家電は家電量販店でまとめて購入する | まとめて購入することで値引き交渉しやすくなる。 |
上記のように引っ越し費用を少しでも節約するために手間をかけてみてはいかがでしょうか。
リフォーム費用を考慮する際のポイント
購入する住宅をリフォームするケースもあります。リフォームすることで、より自分たちの生活にぴったりの家にすることが可能です。リフォームも検討する場合、どのくらいの予算でリフォームするかを考えなければなりません。中古住宅を丸ごとリノベーションする場合、内容によっては1,500万円〜3,000万円かかる場合もあります。
工事場所別だと、キッチンや浴室のリフォームで約50〜150万円、トイレや洗面所で約20〜50万円ほどかかってきます。どの程度の費用をかけるか、資金計画を立てた上で検討しましょう。
仮住まい・引っ越し時の追加費用
今の家を建て替える場合、家が完成するまで仮住まいを探さなければなりません。そうなると、仮住まいで生活している間の家賃負担が発生します。また、今の住まいから仮住まいへ引っ越し、仮住まいから新居への引っ越しで2重に費用負担がかかることも覚えておきましょう。
税金関連の費用とその対策
住宅を購入すると税金が発生します。税金関連の費用とその対策についてみていきましょう。
不動産取得税とは?計算方法と軽減措置
不動産取得税は、不動産を取得した時に課税する地方税です。不動産取得税は、「固定資産税評価額」で算出されます。先にも説明した通り、不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の4%」が基本ですが、令和9年3月31日までは、軽減措置で「固定資産税評価額の3%」の税率になります。
固定資産税評価額は、購入価格の約7割程度の金額になります。また、新築物件を購入した場合の固定資産税評価額は工事金額の5〜6割程度になります。
例えば、土地を1,000万円、新築住宅を2,500万円で購入した場合、軽減措置を適用した上で計算すると以下のようになります。
| 【土地】
1,000万円×0.7×3%=21万円 【建物】 2,500万円×0.5〜0.6×3%=37.5万円〜45万円 |
上記より合計66万円の不動産取得税がかかります。
固定資産税の支払いスケジュール
固定資産税は、納税通知書が毎年4〜5月ごろに市町村から発送されます。手元に届いたら支払いになりますが、一般的に固定資産税は1年分の税額を4期に分割して納付します。
第1期〜第4期までの支払い期限は市町村によって異なるため、納税通知書に書かれている納付期限に従って納付しましょう。1年分をまとめて一括支払いすることも可能です。
住宅ローン控除を最大限に活用する方法
住宅ローン控除は、住宅の購入の目的でローンを組んだ場合に、年末時点の住宅ローン残高に応じて控除される制度です。最大13年間にわたって所得税から控除されます。
住宅ローン控除を最大限に活用する方法はいくつかあります。例えば、住宅ローン控除が適用される13年を経過してから繰上げ返済を行うことで、トータルで見た時に支払い総額を減らせてお得にすることが可能です。また、購入する住宅が以下のような住宅の場合、住宅ローン減税が適用されるのでよりお得になります。
| 2024年〜2025年入居の場合の1年あたりの最大控除額 | |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 21万円 |
購入する物件の性能によっては、日々の光熱費を節約できたり、固定資産税など他の税金の軽減措置も適用される場合があります。入居後のランニングコストもふまえた上で購入する物件を選ぶのも良いでしょう。
贈与税や仲介手数料の仕組み
贈与税・仲介手数料の仕組みについて見ていきましょう。
贈与税
親や祖父母などから年間110万円以上の財産をもらった場合、贈与税を負担しなければなりません。ただし、住宅購入における贈与の場合、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になります。
| 住宅の性能 | 非課税限度額 |
※上記のいずれかであることが証明できる書類が必要 |
1,000万円まで |
| その他の住宅 | 500万円まで |
仲介手数料
住宅購入で負担する仲介手数料は、実は手に入れる方法によっては負担しなくて良くなります。仲介手数料が不要になるケースをまとめてみました。
- 新築マンションや新築戸建てを建設した不動産会社から購入する場合
- 売主が不動産会社で買主との間に他の不動産会社が介入しない場合
- 注文住宅を建てる場合
不動産会社が仲介せずに個人から直接購入する場合も仲介手数料はかかりません。しかし、この場合、トラブルが起きた時にも当事者同士で解決しなければなりません。不動産に関する知識に自信がない場合は、非常にリスクの高い方法なのであまりおすすめしません。
税務署でのアドバイスが役立つ理由
住宅を購入したら、確定申告を行うことでお金が戻ってくる場合があります。例えば、住宅が長期優良住宅や認定低炭素住宅として認められている場合、控除を受けることが可能です。しかし、時には自分の家に確定申告が必要なのかわからないこともあるでしょう。そんな時は、税務署に訪れてアドバイスをもらうことも大切です。税金に関しては専門家に質問することで、お得な情報を手に入れられる可能性もあります。
購入前の計画と費用算出のコツ
最後に購入前の計画と費用算出のコツをご紹介します。
購入予算の立て方と重要なポイント
住宅購入の予算を決める際は、「返済負担率」を意識しましょう。返済負担率とは、年収に対する1年間の住宅ローン返済額の割合のことです。
一般的に無理のない返済負担率は25%以下と言われています。例えば、年収300万円なら「年収300万円×25%÷12ヶ月=62,500円」が無理なく返済できる金額です。ただし、これは住宅ローンだけでなく、車などの他のローンも含めた金額なのでその点は注意しましょう。
また住宅購入の際は、手元に生活費などの予備資金を確保しておくことも重要です。現金で支払う諸費用はもちろんのこと、頭金や生活費半年分などを残しておくと何かあった時に安心できます。
ライフプランに基づく資金計画の作成
住宅購入を計画する際は、ライフプランも考慮しましょう。住宅購入は初期費用だけでなく、住み始めてからのメンテナンス費用や保険料、税金などのランニングコストの負担があります。また、住宅購入だけでなく、結婚や出産費用、子供の教育資金や老後資金など、人生においてさまざまな資金がかかります。
これからのライフプランでどのくらいの費用がかかるのかを想定し、その上で住宅購入の資金計画を立てることが重要です。資金計画を立てないまま住宅を購入すると、ライフステージの変化が影響してローン支払いができなくなって、家を手放さざるを得なくなる可能性もあります。
諸費用の見積もり方法とチェックリスト
住宅購入にかかる費用は、目安として新築物件なら物件価格の3〜7%、中古物件なら物件価格の6〜10%の諸費用がかかってきます。
例えば、3,000万円の住宅を購入する場合、90〜270万円ほどの諸費用がかかるということです。これまで説明したように税金や手数料など、必要なステップで細々と支払っていくため、自分でチェックリストなどを作成しておくと何にどのくらい支払ったのかを確認しやすくなります。これまで解説した項目をノートにまとめるなどして管理をすると良いでしょう。
費用を抑えるための交渉術
住宅購入の費用を抑えるなら、可能な場面での値引き交渉をするのも良いでしょう。例えば、住宅ローンの融資事務手数料や不動産購入時の仲介手数料など、交渉できる場面はいくつかあります。
購入する住宅そのものの値下げ交渉をするのもおすすめです。その場合は、以下のポイントをふまえて交渉してみましょう。
- 売主の売却理由を把握する(できるだけ早く売りたいのかどうかを知れるから)
- 住宅ローン事前審査を通す(住宅ローンの本審査を通せることを売主に伝えて安心感を持ってもらえるから)
- 購入意思の本気度を伝える(手付金の額やリフォームの見積もりを提示して購入意思の強さを伝えて値引き交渉できるから)
値引き交渉をしたいという方は、上記の方法も試してみましょう。
まとめ
住宅購入には本体価格の他に諸費用がかかります。さらに、諸費用は現金であることが多く、住宅の金額によっては数百万円ものまとまった現金が必要なケースもあります。住宅購入時には本体価格だけでなく、諸費用も資金計画に含めて検討するようにしましょう。