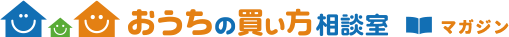住宅購入時にかかる仲介手数料などの諸費用とは?費用の詳細も解説!
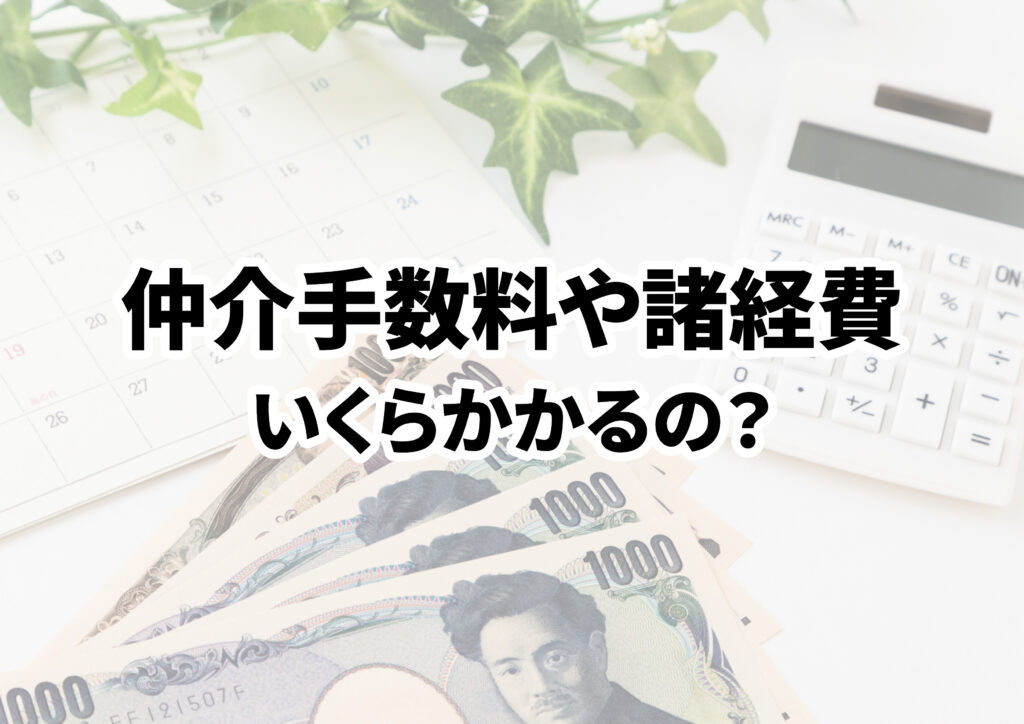
「住宅購入では、どのような費用が必要になるのかわからない」
「仲介手数料とは、誰にいつ支払うお金で、必ず発生するものなの?」
「住宅購入、ローンの申し込み、購入後に必要な費用の情報収集をしておきたい」
住宅購入では、多くの手続きをしなければいけませんが、それぞれに手数料や税金など多くのお金が発生するため、住宅購入費用以外のお金も資金として用意しておく必要があります。そこで本記事では、仲介手数料をはじめとした住宅購入時に必要な費用について解説します。購入後の維持費についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。
住宅購入を検討するには
住宅購入する際には、用意できる頭金や毎月のローン、今後の生活費必要な費用などをトータルで考えて購入予算を決めます。そして、多くの方は予算=物件価格というイメージを持っているのではないでしょうか。
しかし、住宅購入するには物件の価格を支払うだけでなく、さまざまな手続きに費用が発生します。この諸費用がどれくらい必要なのか知らなかったり、諸費用を少なく見積もったりしていると、実際にかかる金額に驚くでしょう。
住宅購入に必要な諸費用は、購入する物件の種類によって手続きが異なるため、差があるものの、一般的に物件価格の3〜10%程度が必要とされています。つまり、3500万円の物件を購入するには、諸費用が5%程度かかった場合約175万円必要ということになります。
「なぜ手続きするだけで、こんなにも費用が必要になるの?」と思った方も多いのではないでしょうか。そこで、次に諸費用の内訳や手続きの内容について詳しく解説していきます。
住宅購入時にかかる諸費用一覧
住宅購入で必要になる諸費用には、どのようなものがあるのでしょうか。まずは、一覧で物件ごとに必要な諸費用の一例を見てみましょう。
| 新築一戸建て | 新築マンション | 中古一戸建て | 中古マンション | |
| 仲介手数料 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 印紙税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録免許税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 司法書士への報酬 | △ | △ | △ | △ |
| 固定資産税・都市計画税清算金 | △ | △ | ○ | ○ |
| 不動産取得税 | △ | △ | △ | △ |
| 修繕積立基金 | × | ○ | × | × |
| 火災・地震保険料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△は諸費用がかかる場合もある
諸費用の詳細と金額の目安
一覧に記載されている諸費用は、それぞれ以下の手続きなどで発生するものです。
仲介手数料
仲介手数料は、売買の仲介をした不動産会社に支払うお金です。一般的には、売買契約時に半分支払い、残りは引き渡し完了時に支払うか、どちらかのタイミングで一括払いするとされています。
なお、仲介手数料の設定額は、宅地建物取引業法で上限が定められています。仲介手数料については、後ほど詳しく解説します。
印紙税
印紙税は、売買で必要な書類(不動産売買契約書・工事請負契約書など)を取り交わす際必要になる諸費用です。金銭のやり取りで使用される書類は課税文書となるため、印紙を貼り付けて税金を支払わなければいけません。印紙税は、取引の額によって異なります。
費用は、2027年3月末までは軽減措置があるため、「1000万円を超え5000万円以下のもの」の契約の場合、1万円です。
登録免許税
登録免許税とは、登記の手続きで必要になる諸費用です。土地や建物の持ち主であることを証明するためには、登記手続きが必要です。そのため、新築物件でも中古物件でも購入する際には、手続きをします。
なお、所有者の登録手続きを「所有権保存登記」といい、建売一戸建てや中古物件など、すでに所有者がいる場合の登録手続きは「所有権移転登記」といいます。それぞれの費用の目安は以下の通りです。
■所有権保存登記
固定資産税評価額×税率0.4%(ただし2027年3月31日まで軽減措置あり)
■所有権移転登記(中古物件など)
固定資産税評価額×税率2%(2026年3月31まで軽減措置あり)
■所有権移転登記(土地)
固定資産税評価額×税率2%(2026年3月31まで軽減措置あり)
司法書士への報酬
上記の登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要になるため、司法書士へ対応依頼する方が多くいます。そのため、司法書士に依頼した分の手数料(報酬)が発生します。
必要な金額は依頼する先や手続きによってまちまちですが、費用の目安は所有権移転登記の場合約5万〜9万円、所有権保存登記であれば約2万円台半ばを目安に考えるとよいでしょう。
固定資産税・都市計画税清算金
固定資産税や都市計画税は、土地・建物を1月1日時点で所有している人が納める税金です。しかし、年の途中に引き渡しがあった場合は清算金が発生するため、購入する物件によって必要になります。金額の目安は、建物の価値(評価額)によって変動します。
■固定資産税
固定資産税評価額×税率1.4%(標準税率)
■都市計画税
固定資産税評価額×税率0.3%(上限)
不動産取得税
不動産を取得した際に必要になる諸費用です。こちらは、取得時に一度だけ支払うもので、固定資産税評価額に4%乗じた金額を支払います。
修繕積立基金
マンションは共用部の大規模修繕をするための費用として、修繕積立金の支払いが必要になるため、入居時に修繕積立基金を支払います。ただし、中古マンションでは修繕積立基金は不要です。
費用の目安は、20〜40万円程度といわれています。戸建の場合は、メンテナンスは自分で行うため、この経費はかかりません。
火災・地震保険料
住宅購入する際には、多くの人が災害時に備えて火災保険と地震保険に加入します。また、住宅ローンを組む際に、加入を必須条件としている場合もあります。なお、地震保険は火災保険とセットになっているため、単独での加入はできません。
■火災保険の目安(10年一括契約の場合)
・一戸建て:10万円程度
・マンション:4万円程度
■地震保険の目安(5年一括契約の場合)
5〜25万円程度
不動産購入時にかかる仲介手数料とは?
住宅購入で必要な諸費用として、税金の支払いは必須であることが理解できても「手数料は誰に払うものなの?」「手数料は絶対支払うものなの?」「安くする方法はないの?」など疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで、諸費用のなかでも「仲介手数料」についての基本知識や、金額の目安などを詳しく解説します。
仲介手数料とは
物件の売買には、売り手と買い手がいます。この売り手と買い手が直接取引して、契約を進めるケースもありますが、間に不動産会社が入り双方の意見調整や交渉、契約の段取りなどを行うケースもあります。この間に入る不動産会社に支払う手数料が仲介手数料です。
なお、売買契約が成立しなかった場合は、不動産会社が仲介に入っていても、手数料は発生しません。あくまで無事に契約が成立したときのみ、手数料を支払います。ちなみに、仲介手数料は物件の売買だけでなく、賃貸物件の場合にも発生します。賃貸契約の初期費用で、敷金や礼金のほか、仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料の支払いがないケースは?
仲介手数料は、全ての物件購入時に必要なわけではありません。仲介手数料が不要なケースの一例は、次の通りです。
■不動産会社から直接購入する場合
新築一戸建てや新築マンションは、不動産会社が建てて、販売しているケースが少なくありません。そのため、不動産会社が管理・販売している物件であれば仲介人がおらず、仲介手数料が発生しません。
■不動産会社が一度購入し、リフォームやリノベーションをして販売している場合
基本的に中古物件は、現在のオーナーが売主となり、仲介人として不動産会社が入って販売するため、仲介手数料がかかります。
しかし、一度中古物件を不動産会社が買い取り、買い手が付くようにリフォームしたり、リノベーションしたりして販売している場合、現在のオーナーは不動産会社ということになります。そのため、このケースも仲介手数料が発生しません。
■売主から仲介手数料を取っている場合
物件の売買では、売主と買主の間に1つの不動産会社が入り、双方から仲介手数料を取るのが一般的です。なお、これを「両手仲介」といいます。そのため、場合によっては売主からのみ仲介手数料を取り、飼い主には仲介手数料を取らないケースもあります。
ちなみに、不動産会社が売主と買主それぞれにいて、不動産会社同士が仲介に入る場合は「片手仲介」といいます。この場合、不動産会社は担当しているいずれかからのみ仲介手数料を受け取ります。
仲介手数料はどのようにして決まるのか
仲介手数料には、定められた金額はなく、仲介している不動産会社が自由に設定可能です。しかし、いくらでも設定可能なわけではなく、定められた金額の上限範囲内でのみ設定ができるのです。
仲介手数料の上限とその計算例
仲介手数料は、仲介している不動産会社が金額設定をしますが、上限があると解説しました。具体的な上限は、宅建業法によって定められており、物件価格によって異なります。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |
| 200万円以下 | 売買価格 × 5% + 消費税 |
| 200万を超え400万円以下 | 売買価格 × 4% + 消費税 |
| 400万円超えの部分 | 売買価格 × 3% + 消費税 |
しかし、物件購入には400万円以上かかるケースでは、基本的には速算式で計算するとよいでしょう。速算式では、「仲介手数料 = 売買価格×3%+6万円 + 消費税」として、計算します。
例えば、3000万円の物件を購入する場合、この式に当てはめて計算すると、仲介手数料の目安は105万6000円ということになります。
仲介手数料は値引き交渉できるのか
先述の通り、仲介手数料は上限こそ定められているものの、具体的な金額の設定はありません。つまり、買主側も不動産会社に交渉し、仲介手数料を値引きしてもらうこと自体に、法的な問題はありません。
しかし、マナーとして過度な値引きをしたり、契約が進んだ段階で無理な相談をしたりするのは避けるようにしてください。無理な交渉をすると、不動産会社からの心象も悪くなり、もし検討中の物件が人気物件だった場合、不動産会社は別の購入希望者と話を進めてしまう可能性もあるでしょう。
そのため、値引きを検討するのであれば、「どうしてもその物件を購入したいけれど、予算を少しだけ上回ってしまう」という相談程度にとどめ、事前に購入予算や用意している諸費用からの予算を伝えてみるようにしましょう。
仲介手数料の支払いのタイミングや支払い方法
仲介手数料は、どのタイミングでどのように支払うのでしょうか。支払いについて詳しく解説します。
仲介手数料はいつ支払うのか
仲介手数料の支払いタイミングに決まりはありませんが、基本的には契約が成立すると支払いが確定するもののため、売買取引が完了する契約時に支払うケースが多いでしょう。ただし、不動産会社によっては引き渡し時に支払いが発生する場合もあるため、あらかじめ不動産会社に確認しておくようにしましょう。
仲介手数料はどのように支払うのか
仲介手数料は、現金一括払いが基本です。しかし、不動産会社によっては「契約時に半金」「決済時に半金」ができる場合もあります。ただし、いずれの場合も現金を用意しておく必要があるため、諸費用として資金を用意しておく必要があります。
支払い方法は、現金手渡しではなく、振り込みができたり振り込みを指定してきたりする場合もあるため、そちらも確認するようにしてください。
また、諸費用は住宅ローンに組み込んだり、諸費用ローンを組んだりできる金融機関があるため、諸費用の準備が難しい場合や手元に現金を残しておきたい場合は検討しましょう。
仲介手数料を払う前に確認したいポイント
仲介手数料の支払いが発生する場合、事前に確認しておきたいポイントを紹介します。住宅購入時に慌てることがないよう、仲介手数料が発生する物件を候補にしている場合は、確認しておいてください。
■基本的に住宅ローンは利用不可
住宅ローンは基本的に物件購入に利用するもののため、仲介手数料をはじめとした諸費用の支払いにあてがうことはできません。そのため、物件購入時には頭金ゼロで購入する場合にも、ある程度の資金を用意しておかなければいけません。
■消費税がかかる
仲介手数料には消費税がかかります。提示金額が税込なのか税抜なのか、きちんと確認しておきましょう。
■仲介手数料ゼロの場合は注意も必要
物件や不動産会社によっては、仲介手数料がかからないケースもあります。これは先述の通り、売主からのみ手数料を取っているというケースが一般的ですが、なかには「仲介手数料は0円だけど、そのほかの手数料や諸費用が多く取られていた」というケースもあります。
そのため、仲介手数料がかからない場合は、そのほかに必要なお金の詳細も確認しましょう。さらに無理な値引き交渉も避けるようにしてください。
住宅ローンに関わる費用
ここまでに、住宅購入で必要になる諸費用について詳しく解説しましたが、住宅購入では多くの方が住宅ローンを利用しています。住宅ローンの契約でもさまざまな費用が必要になるため、そちらも把握して購入を検討するようにしましょう。
住宅ローン契約時に必要な諸費用の総額はどれくらい?
住宅購入で住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの手続きにもさまざまなものがあり、それぞれに手数料などの諸費用が発生します。購入する物件価格やタイプによって異なりますが、一般的には新築の場合、借入価格の約3〜5%程度、中古物件の場合は借入価格の6〜8%程度が費用の目安とされています。
住宅ローン契約時に必要な諸費用の詳細
住宅ローン契約時に必要になるおもな諸経費は、以下のものです。
■金銭消費貸借契約書の印紙税
住宅購入の際に取り交わす売買契約書で印紙税がかかるのと同様に、住宅ローン利用時に必要な金銭消費貸借契約書も、課税文書であるため、印紙税がかかります。借入額によって必要な金額が異なりますが、売買契約書とは異なり、金銭消費貸借契約書には印紙税の軽減措置はありません。
印紙税の目安は、借入額が1000〜5000万円以下の場合2万円、5000万〜1億円以下の場合6万円です。
■抵当権設定の登記費用
住宅ローンを契約して借入したお金で不動産購入する場合、借入先の金融機関によって抵当権が設定されます。抵当権とは、借入金に担保として設定する権利のことで、万が一ローン返済ができなくなったときのために土地や家を担保とするものです。
この抵当権設定登記には、登録免許税がかかりますが「住宅ローンの借入金額×0.4%」で算出できます。
■司法書士への報酬
売買契約時と同様、抵当権設定の登記も司法書士に依頼するのが一般的です。そのため、登記代行の手数料が発生します。なお、費用の目安は7〜10万円程度でしょう。
■融資手数料
融資手数料は、住宅ローンの借入時にその契約先である金融機関に対して支払うものです。なお、金融機関によっては、融資事務手数料や事務取扱手数料という名称の場合もあります。手数料の目安は5万円前後、もしくは借入額の1〜3%程度とされています。
■ローン保証料
ローン保証料は、万が一毎月の返済ができなくなった際に、契約者に代わって金融機関へ債務返済する保証会社に支払うものです。
支払い方法には、契約時に一括で支払う外枠方式に加え、内枠方式という金利に上乗せするものがあります。費用相場は、会社により異なりますが借入額の0〜2%程度で、金融機関によってはゼロの場合もあります。なお、金融機関の住宅ローンではなく、フラット35を利用する場合、この費用はかかりません。
■団体信用生命保険料
団体信用生命保険とは、契約者が住宅ローンの返済期間中に死亡もしくは高度障害になり、返済ができなくなった際、住宅ローン残高をゼロにするための保険です。
多くの金融機関が住宅ローンを組む際の必須条件として、この団体信用生命保険への加入を提示しているため、基本的に保険加入は必須と考えてよいでしょう。保険料は、住宅ローン金利に組み込まれているケースがほとんどです。
特約をつける場合は、特約内容を確認して、自身がすでに加入している生命保険などがあれば、その保証内容と重複しないように気をつけてください。
住宅購入後に必要な維持費も覚えておきましょう
住宅購入では、さまざまな手続きがあり、それらに手数料がかかるため、購入価格のほかにも多くの費用を準備する必要があると解説してきました。
しかし、無事に住宅購入や住宅ローンの手続きが完了し、引き渡しが終わったあとにも税金の支払いやお家の状態維持のためにかかる費用があります。具体的にどのようなものがあるのか、毎年必要な費用と定期的に必要になるものを解説します。
毎年(毎月)必要な費用の一例
毎年(あるいは毎月)必要な費用は次の通りです。毎年支払い忘れや、費用の準備忘れで慌てることがないよう、費用の確保をしておきましょう。
■固定資産税
固定資産税は、土地や建物を所有している人にかかる税金です。この税金は、住んでいる都道府県を問わず、全国どこに住んでいても納税が必要な地方税のひとつです。毎年1月1日時点での所有者あてに毎年4月頃に郵便で通知書が届き、同封されている納税書にて支払います。
納税額は「固定資産評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」で計算できますが、一般的な一戸建て住宅であれば、1年当たり10〜15万円ほどになるでしょう。固定資産評価額とは、土地・面積・形状・建物などの資産価値を評価した上で決められるもので、3年に一度見直しがあります。なお、新築の場合は最初の3年間のみ特例措置で減税対象になります。
■都市計画税
市街化区域内に該当するエリアに家を所有している場合は、固定資産税に加えて都市計画税も毎年納税しなければいけません。都市計画税は「固定資産評価額(課税標準額)×税率(0.3%)」で計算できます。
■修繕積立金
新築マンションの場合、入居時に修繕積立基金としてまとまった額を支払いますが、それとは別に月に1〜2万円ほど支払うのが修繕積立金です。マンションでは、定期的に建物全体をメンテナンスする「大規模修繕」が実施されます。その費用は、住民から毎月徴収する修繕積立金を元とします。
修繕積立金は、常に同じ金額というわけではなく、マンションの築年数が経過すると、必要な修繕が増えていくため、増額していくのが一般的です。
■管理費
管理費とは、マンションの場合のみ毎月発生する費用で、共有部の電気代・水道代などの必要経費や清掃、保守、管理人の人件費などにあてられます。金額は、マンションによって異なりますが、建物の設備が充実しているところほど高額になる傾向にあります。
定期的(数年に一度)に必要になる費用の一例
以下で紹介する費用は、毎年必要なものではありませんが、定期的にまとまった額が必要になるものです。急に準備するのは難しい額のため、計画的に積み立てるなどして準備しておきましょう。
■火災保険・地震保険
多くの場合、住宅購入及び住宅ローン契約時に火災保険・地震保険に加入しますが、更新時期がきたら都度支払いが必要です。火災保険は、毎年支払う方法もありますが、長期一括払い(最長10年)で支払う方が総額を抑えられます。
なお、火災保険は加入するプランによって、火災だけでなく台風や洪水などの自然災害による修理費用もカバーされるため、必要な保証がカバーされているか定期的に見直しましょう。
■メンテナンス費用
例えば、一戸建ての場合、外壁や屋根は10〜15年ほどの周期でメンテナンス(塗装)が必要です。
簡単な補修であれば数十万円ほどでできますが、張り替えなどの大掛かりな工事になれば100万円以上必要になることもあるため、メンテナンス費用として積み立てておくと安心です。
■リフォーム費用
お家の中の設備に関しても、20年以上経つと劣化が目立つようになります。また、劣化した設備を直す目的以外に、老後の生活への対策としてバリアフリー化を検討したり、ライフスタイルや一緒に暮らす家族の人数の変化に伴い、リフォームしたりするケースもあるでしょう。
そのため、まとまった金額の支払いにも対応できるよう積み立てたり、計画を立てたりしておいてください。
まとめ
今回は、住宅購入や住宅ローンの申し込みで必要になる費用や、住宅を所有した際の維持費を解説しました。
仲介手数料は、中古の一戸建てやマンションなどの購入で必要になる費用で、現金払いになるケースも多いため、その他費用の支払いに必要な金額とあわせて準備しておくようにしましょう。また、無事に住宅購入手続きが終わり、暮らしはじめた後も税金や保険の支払い、メンテナンス費用が必要になるため、計画的に費用を準備しておくと安心です。