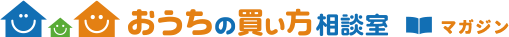注文住宅の価格はいくらかかる?相場と費用の内訳を徹底解説!
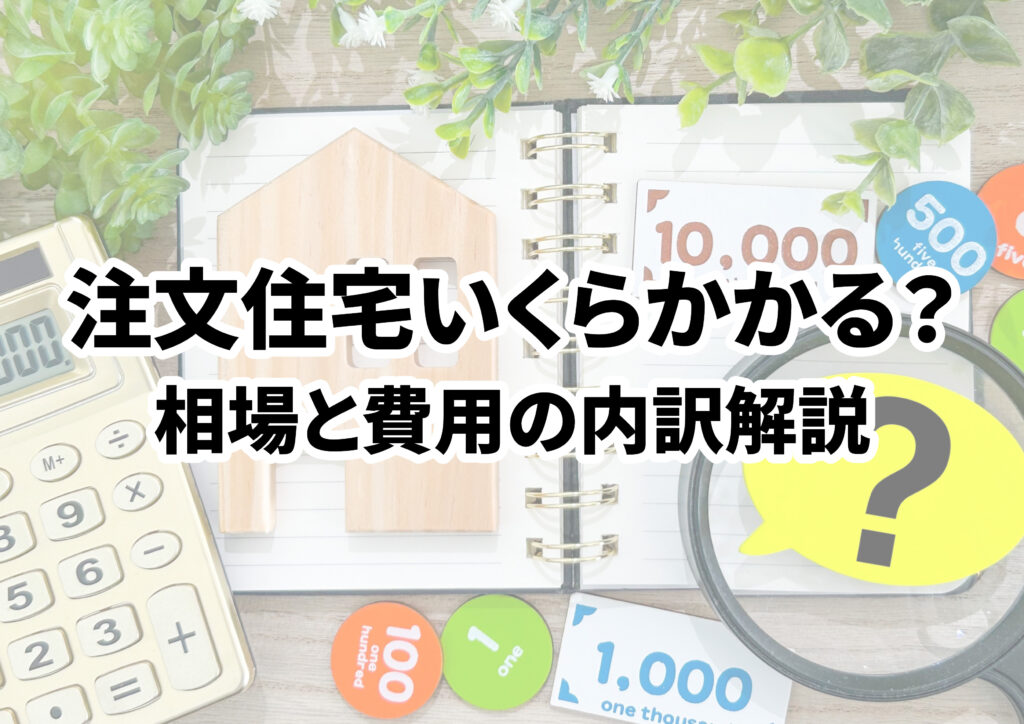
「注文住宅の相場を知りたい!」
「価格の内訳はどうなっている?」
「予算の決め方がわからない…」
あなたは注文住宅について、このように感じたことはありませんか?注文住宅は、自由に設計できるのが最大の魅力です。間取りや外観、内装まで自分の好きなようにカスタマイズができます。愛着のある家づくりに繋がるため、完成後の満足度も高くなるでしょう。
ですが、家づくりを検討し始めた方にとっては、何から手をつけていいか分からない方も多いと思います。予算の決め方や資金計画、業者選びなど、やるべきことはたくさんあります。
特に気にしているのは、注文住宅の価格ではないでしょうか。住宅の購入は、人生の中で最も大きな買い物になります。家づくりに失敗しないためにも、相場や費用の内訳が気になるのは当然のことです。
そこで本記事では、注文住宅の価格相場や内訳、予算の決め方、資金計画について解説していきます。本記事を参考に、注文住宅を建てる際の参考にしてみてください。
注文住宅の価格相場
注文住宅は土地の有無によって、価格が大きく変わります。そのため、ご自身の状況にあった相場を知ることが重要です。ここでは、「土地を持っていない場合」と「土地を持っている場合」の価格相場について解説します。
土地を持っていない場合の価格相場
「2023年度 フラット35利用者調査」によると、土地を購入する場合の注文住宅の全国平均価格は約3,405.8万円です。地域別に見ると、以下のとおりになります。
| 地域 | 建築費の相場 | 土地の相場 |
| 全国平均 | 3,405.8万円 | 1,497.6万円 |
| 三大都市圏 | 3,423.0万円 | 1,995.7万円 |
| 首都圏 | 3,402.3万円 | 2.277.3万円 |
| 近畿圏 | 3,414.5万円 | 1,850.8万円 |
| 東海圏 | 3,491.1万円 | 1,319.4万円 |
| その他地域 | 3,384.0万円 | 915.3万円 |
建築費を全国平均と比較すると、地域による価格差はそれほど大きくありません。ですが、土地の価格は、エリアによって大きく異なります。土地代を含めると、相場は4,500万円〜5,500万円程度になります。特に首都圏などの都市部では土地価格が高い傾向にあるため、希望するエリアによってはより多くの資金が必要です。
参考:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査 土地付注文住宅 集計表
土地を持っている場合の価格相場
すでに土地を所有している、もしくは建て替えを検討されている方もいらっしゃるでしょう。
「2023年度 フラット35利用者調査」では、建物のみの全国平均価格は約3,861.1万円となっています。地域ごとの相場は、以下のとおりです。
| 地域 | 価格相場 |
| 全国平均 | 3,861.1万円 |
| 三大都市圏 | 4,109.7万円 |
| 首都圏 | 4,190.2万円 |
| 近畿圏 | 4,142.1万円 |
| 東海圏 | 3,893.4万円 |
| その他地域 | 3,623.8万円 |
土地の購入が必要ないため、平均価格は土地を持っていない場合と比べると高めです。建物本体や設備にかける予算が増え、結果として建築費用が高くなっていると考えられます。
参考:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査 注文住宅 集計表
注文住宅の価格内訳
注文住宅の価格内訳は、大きく分けて以下の4つになります。
- 本体工事費用
- 付帯工事費用
- 諸費用
- 土地購入費用
本体工事費用
注文住宅の中で最も大きな割合を占めるのが「本体工事費用」です。建物そのものを建てるために必要な費用で、具体的には以下のような工事が含まれます
- 基礎工事
- 構造体、骨組み
- 屋根、外壁
- 断熱材
- 内装の仕上げ(床や壁、天井など)
- 住宅設備(キッチン、トイレ、浴室など)
本体工事費用は、建物の規模や使用する材料のグレードによって、工事の費用は大きく変動します。たとえば、同じ間取りでも、キッチンをグレードの高いものにすると、数十万の差が出ることも珍しくありません。
注文住宅の魅力は、自由に設計ができることですが、デザインにこだわりすぎると、予算オーバーになる可能性があります。そのため、デザイン性とコストのバランスを意識しながら、仕様や間取りを決めていきましょう。
付帯工事費用
付帯工事は「住宅本体以外に必要な工事」のことで、主に以下のような工事が含まれます。
- 地盤調査、改良工事
- 給排水工事
- 外構工事
- 造園工事
- 電気工事
- 解体工事(建て替えの場合)
目に見えにくく見落とされがちですが、想定外に出費になりやすい部分です。地盤の状態の状態によっては、地盤の改良工事が必要になり、追加費用が発生するケースも珍しくありません。
また、建て替えの場合は、既存の建物を取り壊す「解体工事」が必要になります。解体費用は構造や規模によって異なるため、見落とせない費用の一つです。
諸費用
注文住宅の購入時には、税金やローン、保険料などの諸費用の把握も重要です。諸費用に該当するのは、主に以下のとおりになります。
- 印紙税
- 登記費用
- 不動産取得税
- 火災保険、地震保険料
- 住宅ローンの手数料
- 引っ越し費用
建て替えの場合は、工事期間中の仮住まいの家賃や仮住まいへの引っ越し、新居への引っ越し費用も必要になります。また、新居での生活に必要な家具や家電の購入費用も考慮しておきましょう。
土地購入費用
土地購入費用とは、単に土地そのものの価格だけでなく、購入に関わる諸費用すべてを含んだ総額を指します。土地を購入する際には、主に以下のような費用が発生します。
- 土地代金
- 印紙税
- 登記費用
- 仲介手数用
- 固定資産税
土地を購入する際は、土地代金だけに注目して予算を組んでしまうと、建物自体にかけられる予算が足りなくなってしまいます。
たとえば、「もう少しグレードの高い外壁材を使いたかった」「こだわりのキッチンを諦めないといけなかった」といったように、希望するデザインが実現できなくなる可能性もあります。
そのため、土地購入の費用を検討する際は、土地代金だけで判断せず、その他の費用を含めた総額で考えましょう。
注文住宅の坪単価について
注文住宅を建てる際、価格を把握するための指標となるのが「坪単価」です。坪単価の概要や計算方法、ハウスメーカーと工務店で価格が異なる理由を解説します。
坪単価とは1坪あたりの建築費用
坪単価とは、1坪あたりにかかる建築費用のことです。坪単価がわかれば、住宅を建てる際の費用の把握に役立ちます。坪単価の計算方法は、以下のとおりになります。
坪単価=本体工事費用÷延床面積(坪数)
たとえば、建物本体の工事費が2,000万円、坪数が40坪の場合では、
2,000万円÷40坪=50万円
という計算になります。
注文住宅の坪単価に含まれるのは、一般的には「建物本体の工事費用」のみです。外構工事や地盤改良工事などは、本体工事費用に含まれません。
ハウスメーカーと工務店によって価格が異なる
注文住宅の依頼先は、「工務店」もしくは「ハウスメーカー」が主流となっています。注文住宅の坪価格は、依頼先によって価格が異なります。
依頼先ごとの坪単価の目安は、以下のとおりです。
- ハウスメーカー:60~100万円程度
- 工務店:40~70万円程度
坪単価は工務店に比べると、ハウスメーカーのほうが高額な場合が多いです。なぜなら、ハウスメーカーは全国規模で展開しているため、広告費や展示場の運営費が建築費用に上乗せされているからです。費用は高くなりますが、施工の流れがシステム化されているので、品質を均一に保ちやすいです。また、アフターサービスが手厚く、完成後の定期点検にも対応しています。
一方で、工務店の場合は地域密着型が多く、ハウスメーカーと比べて、坪単価は安い傾向にあります。というのも、工務店は広告費をあまりかけていないからです。ハウスメーカーよりも自由度も高く、家づくりに細かくこだわりたい方にぴったりです。
ただし、施工の技術や完成後の対応は業者によってばらつきがあるため、選ぶ際は注意が必要です。安心感やブランド力を重視したい方はハウスメーカーを、少しでもコストを抑えたい方や自由度の高い家づくりを望む方は工務店を選ぶとよいでしょう。以下の記事で、会社の選び方を解説しているので、あわせて読んでみてください。
【2024 年版】住宅購入のハウスメーカー選びを徹底解説!選び方のポイントも紹介!
注文住宅と建売住宅の違い
注文住宅と建売住宅の違いは、主に以下のとおりになります。
| 住宅の種類 | 特徴 |
| 注文住宅 |
|
| 建売住宅 |
|
注文住宅は一から設計や建築をする住宅
注文住宅は設計や間取り、土地選びなどをすべてご自身で決められます。床や外壁の素材、キッチンやお風呂などの設備を予算と好みに合わせて選べるのが特徴です。完成済みの建売住宅とは違い、完全オリジナルの家が建てられるのが最大のメリットと言えるでしょう。
また、将来のライフステージの変化を見据えた設計もできます。たとえば、将来的に子供が生まれる予定があるなら、部屋数を多めに確保するのもよいでしょう。老後を考えて、住宅の段差をなくしたり、手すりを設置したりなどのバリアフリー対策も行えます。
ただし、一から設計と建築を行うため、完成までには時間がかかります。また、こだわりすぎると費用が高くなりやすいため注意が必要です。予算オーバーにならないよう、使用する材料や設備のグレードを下げることも検討しましょう。
建売住宅は土地と建物がセットになっている住宅
建売住宅は土地と建物がセットで販売されているため、完成品を見てから購入をします。設計や土地選びの必要がなく、間取りや設備などの仕様があらかじめ決められてるため、購入手続きが完了すればすぐに入居ができます。
完成済の物件を実際に見学して、間取りや設備、日当たりなどを確認できるので、入居後のイメージとのギャップも少なくなります。
一方で、設計や設備があらかじめ決まっているため、希望する物件を探すまでに時間がかかってしまうでしょう。また、建売住宅は似たようなデザインの物件が多く、自分好みへのカスタマイズも難しいです。個性的なデザインを求める場合は、物足りなさを感じてしまうかもしれません。
注文住宅と建売住宅の価格差
注文住宅と建売住宅の価格差について。気になる方もいらっしゃるでしょう。まずは、建売住宅の価格相場についてご紹介します。地域ごとの相場は以下のとおりです。
| 地域 | 建売住宅の価格相場 |
| 全国平均 | 3,603.2万円 |
| 三大都市圏 | 3,878.9万円 |
| 首都圏 | 4,199.3万円 |
| 近畿圏 | 3,720.8万円 |
| 東海圏 | 3,055.1万円 |
| その他地域 | 2,873.0万円 |
注文住宅と同様に、首都圏での相場は高めです。全体の相場としては、3,000万円~4,000万円程度になります。
注文住宅は土地付きの場合、相場は4,500万円〜5,500万円程度です。建売住宅に比べると、1,000万円〜1,500万円以上の価格差があります。自由に設計できる分、注文住宅の価格は高くなりやすいです。
建売住宅は、あらかじめ決められた設計や使用で建てられています。コストの削減がしやすく、注文住宅に比べて価格は安く設定されています。
参考:住宅金融支援機構 2023年度フラット35利用者調査 建売住宅 集計表
注文住宅の予算を決めるための5つのステップ
注文住宅は理想の家を形にできる一方で、日々の生活に影響が出ない範囲での予算決めが大切になります。ここでは、予算の決め方を5つのステップでご紹介します。
STEP1:収入と支出のバランスを考える
注文住宅の予算を決める最初のステップは、ご自身の収入と支出のバランスを把握することです。多くの方は住宅ローンを利用して注文住宅を建てますが、無理のない返済計画を立てるためには、現在の経済状況をしっかり理解しておく必要があります。
具体的には、以下の内容をチェックしましょう。
- 世帯収入(共働きの場合は合算)
- 生活費や教育費などの月々の支出
- 現在の貯蓄額と毎月の貯蓄額
現在の貯蓄額の把握は、どれくらいの頭金が用意できるのか、緊急時の備えがあるかの確認に役立ちます。
STEP2:希望するエリアを決める
収入と支出のバランスが把握できたら、次は希望するエリアを決めていきます。注文住宅を建てる上で、場所選びは非常に重要です。なぜなら、一度住宅を建ててしまうと、場所の変更はできないからです。
希望するエリアによっては、土地の価格相場は大きく異なるため、予算設定に直接影響してきます。また、価格だけでなく、立地や周辺環境のチェックも欠かせません。通勤や通学の利便性、騒音の有無、買い物しやすさなども考慮しましょう。
STEP3:注文住宅の建築プランを建てる
土地選びの次は、注文住宅の建築プランを立てていきます。理想の住まいを形にするには、「どんな家にしたいのか」を明確にする必要があります。家族構成やライフスタイルに合わせて、必要な部屋の数や間取り、設備などをイメージしてみましょう。
ある程度イメージが固まったら、依頼する会社に相談をしてみてください。おおよその費用がわかり、予算の計画も立てやすくなります。
STEP4:住宅ローンの借入額を決めていく
収支のバランスと希望エリアが決まったら、住宅ローンの借入額を決めていきます。住宅ローンを組む際は、頭金の有無も大切なポイントです。頭金を用意できれば、住宅ローンの借入額が少なくなるため、毎月の返済負担を軽減できます。
頭金なしでもローンを組めますが、毎月の返済額が増えるため、家計を圧迫する可能性があります。さらに、購入後は修繕費や保険料などの維持費も発生するため、手元資金が少ないと、万が一の事態に対応できなくなります。
将来の返済計画や日々の生活への影響を考慮して、住宅ローンの借入額は慎重に検討しましょう。
STEP5:建物とと土地の予算配分を決める
全体の予算が見えてきたら、建物と土地の予算配分を決めていきます。予算のバランスが悪いと、希望するエリアに手が届かなかったり、材料のグレードを下げたりしないといけなくなります。
建物と土地の予算配分は、建物が6〜7割、土地が3〜4割程度が目安になります。地域ごとに土地の価格は異なるため、希望するエリアの土地価格の確認は欠かせません。
また、材料や設備にこだわり過ぎると、土地の購入にあてる費用が足りなくなってしまう場合もあります。そのため、予算内に収まるように調整が必要です。
注文住宅を建てるための資金計画
注文住宅を建てる際には、資金計画が非常に重要です。無理のない返済計画を立て、将来の生活にも余裕を持たせるためには、綿密な資金計画が欠かせません。
ここでは、注文住宅の資金計画について、具体的なポイントを詳しく解説します。
住宅ローンの返済額をシュミレーションする
注文住宅を建てる際、多くの方が住宅ローンを利用します。無理のない返済計画を立てるためには、「返済負担率」を考慮することが大切です。
返済負担率とは、年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合を示す数値です。一般的に、返済負担率は25〜35%程度が理想的とされています。計算方法は、以下のとおりになります。
返済負担率=年間返済額÷年収×100%
住宅ローンの返済額のシミュレーションは、無理のない資金計画を立てる上で必要不可欠です。なぜなら、住宅の購入は数千万円の高額な買い物であり、返済期間も長期にわたるからです。資金計画が適切でないと、家計を圧迫してしまうため、日々の生活に影響が出てしまいます。
事前に入念な計画を立てておけば、家計に余裕を持たせながら、無理なく返済を進められるでしょう。
物件以外にかかる費用を明確にする
注文住宅では、土地や建物の価格だけでなく、様々な費用が発生します。これらの費用を事前に把握しておかないと、予想外の出費に苦しむことになりかねません。
土地や物件以外にかかる費用は、主に以下のとおりです。
- 外構工事費
- 地盤調査、改良費
- 登記費用
- 火災保険、地震保険料
- 引っ越し費用
- 家具や家電の購入費
また、屋根や外壁のメンテナンス費用や修繕費用も含めた計画も重要です。万が一の状況にも対応できるよう、建物以外の費用も考慮した資金計画を立てましょう
税制優遇制度を活用する
注文住宅を購入する際には、様々な税制優遇制度を受けられます。制度を上手に活用すれば、全体のコストを抑えられ、費用の節約に繋がります。
注文住宅の購入時に活用できる制度は、主に以下のとおりです。
- 住宅ローン減税
- 登録免許税の軽減措置
- 不動産取得税の軽減措置
- 印紙税の軽減措置
- 固定資産税の軽減措置
年度によって金額や条件が変更されたり、期限が設定されていたりするため、最新の情報を確認するようにしましょう。
こちらの記事で、住宅関連の税制優遇について解説しています。資金計画のメリットや資金不足が招くリスク、ローンの種類について解説しているので、あわせて読んでみてください。
注文住宅の会社選びで失敗しないためのポイント
注文住宅は、自由度の高い家づくりができる反面、会社選びを間違えると「こんなはずじゃなかった…」といった後悔に繋がります。
ここでは、注文住宅の会社選びで失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
施工実績や口コミ、評判を確認する
会社選びで欠かせないのは、過去の施工実績や利用された方の口コミです。会社のホームページから、価格帯や施工内容をが確認できます。「どんなデザインで手掛けているか」「価格はどれぐらいなのか」など、より具体的な内容もわかるでしょう。
写真を掲載していたり、工事内容が詳細に書いてあったりすれば、信頼できる会社と判断してもよいでしょう。施工事例が詳細に掲載されている会社なら、自社の技術に自信を持っている証拠になります。
また、利用された方の口コミも参考になります。工事の内容やスタッフの対応など、実際に利用されたからこそわかる、生の声を知ることができます。長期間のお付き合いとなるため、スタッフがどのような対応をしてくるのかも重要です。
1社で決めずに相見積りを取る
注文住宅の会社選びは、1社で決めずに相見積りを取るようにしましょう。なぜなら、相見積りで相場の把握ができ、価格の比較もできるからです。同じ条件であっても、会社によって価格が異なる場合があります。
複数社と比較すれば、ご自身の予算にあった家づくりができ、費用の節約に繋がります。相見積りの数は、3社程度がおすすめです。というのも、相見積りの数が多すぎると比較が難しく迷ってしまいます。より多くの時間が必要になるため、相見積りは3社までにしましょう。
保証やアフターサービスの内容をチェックする
住宅の完成後も長く安心して暮らすためには、保証やアフターサービスもチェックすべき内容です。保証の内容としては、以下の項目を確認してみましょう。
- 保証の長さや対象範囲
- 定期点検の頻度
- アフターサービスの内容
- 緊急時のサポート体制
価格だけでなく、完成した後の対応も重要です。契約前には、保証の内容やサポートの流れなど、しっかり確認してみてください。
まとめ
本記事では、注文住宅の価格相場や内訳、坪単価について解説しました。注文住宅は設計や土地選びなどを一から行うため、ご自身の好みを取り入れやすいです。子どもの成長や老後など、ライフステージの変化にあわせた設計もできます。自由度が高い反面、こだわりすぎると費用が高くなりやすく、予算オーバーに繋がります。
また、土地や建物以外にも費用がかかるため、事前の把握も必要です。会社選びで失敗しないためにも、相見積りを取って、価格や対応などを比較するようにしましょう。
おうちの買い方相談室では、一般住宅に関するお悩みへのアドバイスを行っております。基本、相談は無料で、初めての方でもお気軽にご利用いただけます。気になる方は、お電話やWEBでお問い合わせください。