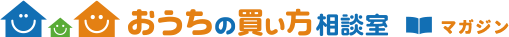住宅購入の資金計画で失敗しない!ローンの種類や選び方を解説
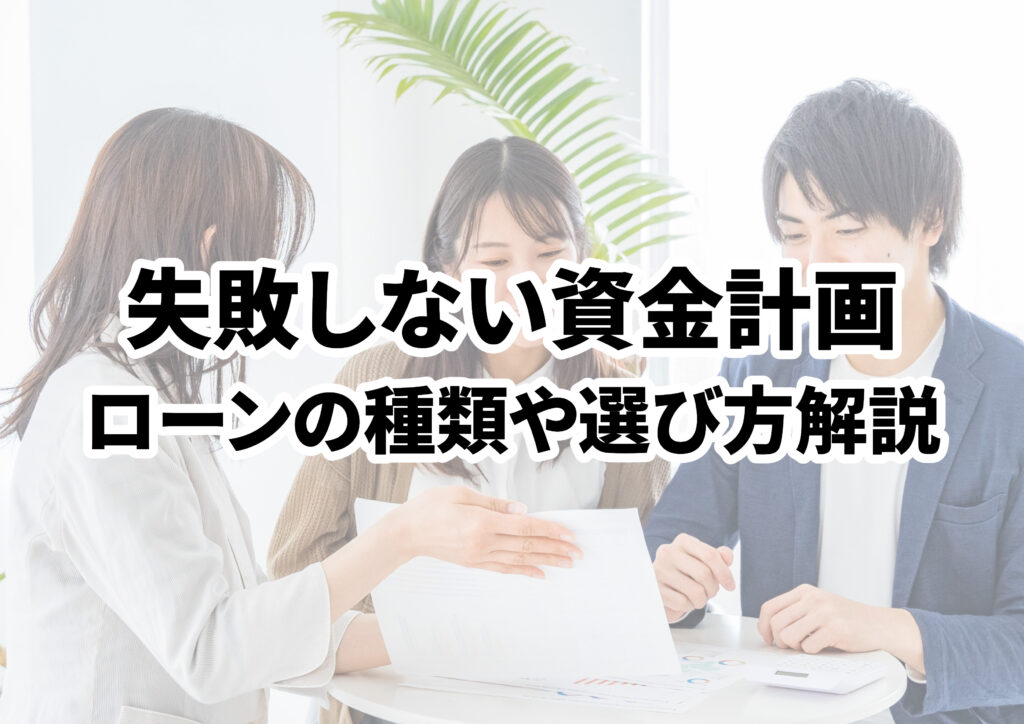
「住宅購入で失敗しないための資金計画を知りたい!」
「ローンの選び方はどうすればいい?」
「購入後の生活が不安...」
あなたは、このような悩みをお持ちではないですか?住宅購入は人生の中で最も大きな買い物で、多くの費用が必要です。初めてのことばかりで、どのように資金計画を立てればいいか、わからない方もいらっしゃると思います。購入後も住宅ローンの返済や火災保険料、固定資産税などの支払いを無理なく続けられるのか、不安になってしまいますよね。
そこで本記事では、住宅購入の資金計画でお悩みの方に向けて、返済計画の立て方やローンの選び方、種類について詳しく解説していきます。資金計画でお困りの方は、この記事を参考にしてみてください。
住宅購入における資金計画の重要性
住宅購入で資金計画を立てる際には、住宅ローンの返済以外にも、生活資金の確保や購入後の維持費を考慮しないといけません。資金計画なしで進めてしまうと、毎月のローン返済が苦しくなったり、維持費で思わぬ出費が発生したりするなどのトラブルが起きやすくなります。万が一のリスクに備えて、資金計画は入念に立てておきましょう。
資金計画を立てることで得られるメリット
住宅購入をする際に資金計画を立てておくと、以下のようなメリットが得られやすくなります。
- 無理のない返済計画を立てられる
- 購入後の生活資金を確保できる
- 予算に合った住宅を選べる
無理のない返済計画を立てられる
現在の収入にあわせて住宅ローンに設定すれば、家計に余裕ができ、無理のない返済を進められます。事前に資金計画を立てておくと、ローンの額が明確になるため、無計画のローンを組むよりも、家計が破綻するリスクを最小限にできます。
ボーナスの減額や子どもの教育費などの出費にも対応できるため、万が一のリスク回避にも繋がります。投資に回せるお金も確保できるため、将来のライフイベントにも対応できるでしょう。また、生活防衛資金も確保できるため、転勤や転職などの突発的なイベントにも備えられます。
購入後の生活資金を確保できる
資金計画を立てておくと、購入後の想定外の出費に対応ができます。たとえば、以下のような費用に備えられます。
- 固定資産税
- 修繕費
- 火災保険、地震保険
- 駐車場代
- 管理費(マンションの場合)
戸建ての場合、外壁や屋根の修理は築10〜15年ほどが目安です。あらかじめ修理の計画を立てておけば、大きな支出にも対応でき、万が一のリスクにも備えられます。購入後の生活資金を確保すれば、急な出費に備えられるため、生活設計もしやすくなります。家計の安定にもつながるため、購入後も安心して生活ができるでしょう。
予算に合った住宅を選べる
予算を明確にすると無駄な出費を抑えつつ、最適な住宅選びに繋がります。住宅ローンを使用する場合は、ローンの種類や金利を比較して、今の経済状況にあった条件で借りられます。
「金利上昇で生活に不安を抱えたくない」という方は、低金利のローンを選ぶのもよいでしょう。登記費用や火災保険も含めて予算に組み込んでおくと、予算オーバーを防げます。子どもの教育費や老後資金も考慮すれば、住宅ローンの返済額をより正確に設定できます。
予算が明確になれば、無駄な出費を抑えつつ、最適な住宅を選べるでしょう。予算の組み方を詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせて読んでみてください。住まい選びや土地探しのポイントもあわせて解説してあります。
初めての住宅購入!家づくりで押さえるべきポイント 7 項目を徹底解説
https://ouchino-kaikata.com/magazine/blog/1653.html
資金不足が招くリスクとその対処方法
資金不足が起きると、頭金の不足し、借入額が増えてしまいます。月々の返済額も増えてしまうため、生活に支障が出てしまう恐れがあります。また、火災保険料や固定資産税などの維持費で、想定外の出費が発生することも考えられます。
住宅ローンの返済が苦しくなる
年収に対して無理な借入額を設定してしまうと、毎月の返済が苦しくなり、家計を圧迫してしまいます。生活費が不足する可能性もあり、ローン返済が難しくなります。
また金利が上昇した場合、注意が必要です。変動金利の住宅ローンだと、低金利の状態から上昇すると、金利が数%上がるだけで大幅に返済額が増えてしまいます。住宅ローンを使用する際には、収入に合った借入額に設定し、金利上昇時のシミュレーションが大切です。金利上昇のリスクを避けたい方は、金利が変わらない「固定金利」を検討するのもよいでしょう。
頭金不足による借入額の増大
頭金を多く用意できれば、住宅ローンの借入額は少なくなります。ですが、頭金が少ないもしくはゼロの場合、不足している分を住宅ローンで補わないといけません。そのため、住宅ローンの借入額は増えてしまいます。
4,000万円の住宅を購入する場合を例にあげると、以下のとおりになります。
- 頭金800万円→借入額3,200万円
- 頭金200万円→借入額3,800万円
- 頭金ゼロ→借入額4,000万円
住宅購入では物件価格以外にも、火災保険や登記費用、引っ越し費用などの諸費用も考慮しないといけません。諸費用の目安は3〜8%程度です。物件の価格だけでなく、諸費用を含めた予算計画を立てましょう。頭金が少ない場合は新築住宅だけでなく、中古住宅も検討してみてください。
維持費による想定外の出費
住宅購入では物件の価格やローン返済に目が行きがちですが、購入後の維持費も考慮しないといけません。維持費を考慮しないと、「マイホームでこんなにお金がかかるとは思わなかった」と想定外の出費に苦しんでしまいます。
住宅購入後に発生する維持費は、主に以下のとおりです。
- メンテナンス、修繕費
- 火災保険、地震保険料
- 固定資産税
マンションの場合では、管理費や修繕積立金、駐車場代などが維持費に該当します。賃貸とは違い、修繕やメンテナンスはすべて自己負担になります。物件価格や住宅ローンを考えることも大切ですが、購入後の維持費を考慮して資金計画を進めましょう。
無理のない返済額の考え方
返済額を決める際には、「返済負担率」を重視するようにしましょう。返済負担率とは、年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合のことです。計算方法は以下のとおりです。
返済負担率(%)= 年間返済額 ÷ 年収 × 100
25〜35%以下が理想的な返済負担率と言われています。たとえば、住宅ローンの返済額が120万円で、年収が500万円の場合、返済負担率は24%になります。ただし、生活費や教育費、他のローンを考慮して判断しましょう。
住宅購入後の返済額を決定するためのステップ
住宅購入後の返済額を決めるには、収入と支出のバランスを把握し、適切な頭金と借入額の比率を決めて、無理のない返済期間の設定が重要です。それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
収入と支出のバランスを把握する
返済額を決めるには、まず現在の収入と支出の状況を把握する必要があります。住宅ローンの返済額は年収の25〜35%が目安とされています。収支の確認では、以下の項目をチェックしましょう。
- 世帯収入(共働きの場合は収入を合算)
- 生活費や教育費などの支出
- 現在の貯蓄額と毎月の貯蓄額
収支の把握ができたら、返済負担率から月々の支払額を設定します。年収500万円を例に、返済負担率25〜35%で計算すると、年間の返済額は125〜175万円、月々の支払いは約10〜15万円が目安となります。
頭金と借入額の適切な比率
住宅購入時の頭金は住宅価格の20〜25%が目安とされており、借入額は75〜80%が適切と言えます。たとえば、住宅価格が4,000万円の場合、頭金は800〜1,000万円程度になります。
頭金なしでも住宅ローンを組めますが、借入額が増えてしまい、毎月の返済負担も大きくなります。変動金利を選択していると、金利の上昇に伴い、支払総額も増えてしまいます。借入額が多いとローンの審査も通りにくくなるため、ある程度の頭金は必要です。
頭金の金額を決める際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 月々の返済額のシミュレーション
- 子供の教育費や老後などのライフプランの考慮
- 購入後の諸費用の把握
「ローンの総額を減らしたい」「審査が通るか不安」と思う方は、頭金を増やして住宅ローンを組むとよいでしょう。貯蓄が少なく、火災保険や地震保険、引っ越しなどの諸費用に回したい場合は、頭金を抑えめにする選択肢もあります。
返済期間の設定をする
住宅ローンの借入期間は、一般的に35年が最長ですが、近年では50年の長期ローンも登場しており、ローンの長期化が進んでいます。返済期間を長くすると毎月の返済額を抑えられ、収入に対する住宅ローンの割合も小さくなります。
ですが、返済期間が長くなると支払う利息の総額も増えてしまうため、期間の設定には注意が必要です。一方で返済期間を短くすると、ローンを早く完済できるメリットがありますが、毎月の返済額は増加してしまいます。資金に余裕があり、定年後の返済に不安がある場合は、繰り上げ返済の活用も検討してみましょう。
住宅購入で使用できるローンの種類と選び方
住宅購入には多くの資金が必要なため、ほとんどの方が住宅ローンを利用します。住宅ローンには様々な種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。ご自身の状況や希望に合わせた住宅ローン選びも大切です。
住宅ローンの種類
住宅ローンは主に以下の3種類に分けられます。
- 民間金融機関の住宅ローン
- 公的融資
- フラット35
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
民間金融機関の住宅ローン
メガバンクや地方銀行、信用金庫などの金融機関が提供する住宅ローンは、様々な商品が用意されており、選択肢も豊富です。
各金融機関の競争が激しいため、公的融資などと比べて金利が低い傾向にあります。低金利のローンを探している方におすすめです。ただし、金利上昇のリスクもあるため、慎重に検討しましょう。
公的融資
公的融資とは、国や自治体が提供する住宅ローンを借りることです。公的融資には、「財形住宅融資」があります。財形住宅融資は、5年ごとに金利を見直す5年間固定金利制です。財形貯蓄制度を1年以上利用していて、一定の条件を満たす方が利用できます。
新築住宅の建設や購入に使用でき、貯蓄残高の10倍までの額、最高で4,000万円までを比較的低金利で借りられます。ですが、申込日時点で、貯蓄残高が50万円以上必要なため、利用前は残高の確認も行いましょう。
フラット35
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型の住宅ローンです。返済期間の金利が確定しているため、毎月の返済額が一定のままです。
新築・中古どちらにも利用可能で、頭金が少なくても利用できるのが特徴です。審査もゆるく、自営業や勤続年数が短い場合でも申し込みができます。「金利上昇で生活に不安を抱えたくない」「無理のない資金計画を立てたい」という方に向いていると言えます。
変動金利と固定金利の選択基準
住宅ローンでは、変動金利と固定金利のどちらを選ぶかも重要なポイントです。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身にあった金利のタイプを選びましょう。
変動金利の特徴
変動金利は固定金利に比べて金利が低く、金利が下がれば返済額も減少するメリットがあります。変動金利は、短期間の返済に向いているのも特徴です。
一方で、金利上昇のリスクがあるため、返済額が不安定になりやすいです。そのため、長期間の借り入れには不向きと言えます。
固定金利の特徴
固定金利は金利が変わらないため資金計画が立てやすく、金利上昇の影響を受けなくなるため、長期間の借り入れに向いています。
ただし、変動金利より金利が高く、金利が下がっても返済額は減らないデメリットもあります。返済額を一定に保ち、安定した返済計画を立てたい方は固定金利が選ぶとよいでしょう。
借り換えの効果とタイミング
住宅ローンの借り換えとは、現在契約しているローンから新しいローンに切り替えることです。借り換えは金利を低く抑えて返済総額を減らしたり、金利上昇のリスクを回避したりするなどのメリットがあります。
低金利の住宅ローンに変更すれば、毎月の返済額が減るため、家計の負担も軽くなるでしょう。借り換えができる具体的な期間は決められていないため、金融機関が定める条件を満たせば、借り換えを行えます。
借り換えをするタイミングは人それぞれですが、以下のタイミングだと、借り換えのメリットを受けやすくなります。
- より条件の良い住宅ローンを見つけた
- 固定金利期間が終了する
- 転職を検討している
- 住宅ローンの借入時より、金利が下がっている
- ローンの残高が1,000万円以上で、返済期間が10年以上残っている
借り換えの際は事務手数料や保証料、登記費用、印紙税などの諸費用が発生します。これらの費用を考慮せずに借り換えると、かえって損をしてしまう可能性もあります。借り換えを検討する際は、事前に十分な確認を行うようにしましょう。
住宅購入の資金計画を立てるための方法
住宅購入では、住宅ローンの返済とあわせて、保険料や税金などの様々な費用がかかります。無理なく返済を続けるためには、購入価格だけでなく、頭金や諸費用を含めた資金計画が必要です。
ここでは、資金計画の立て方や住宅購入時に活動できる税制優遇制度について解説していきます。
資金計画を立てるときのポイント
頭金が不足していると、現在の収入に合わないローンを組もうとしても、審査が通らない場合があります。仮にローンが通ったとしても、毎月の返済が難しくなってしまうでしょう。
生活が苦しくなるだけでなく、将来的なライフプランにも悪影響を及ぼす可能性があります。
住宅購入の前には、しっかりとした資金計画を立てておくことが重要になります。なぜなら、子供の教育費や老後資金の確保が難しくなり、怪我や病気などの急な出費への対応が難しくなってしまうからです。
資金計画では現在の収入や支出だけでなく、将来的にかかる費用も考えておかないといけません。保険料や不動産所得税、固定資産税などの諸費用も考慮しないと、購入後の資金が足りなくなる恐れもあります。住宅購入で大きなストレスを抱えないためにも、購入価格だけでなく、頭金や諸費用も含めた資産計画は必要不可欠と言えます。
住宅関連の税制優遇を活用する
住宅購入で使える税制優遇制度は、主に以下の5種類になります。
- 住宅ローン減税
- 登録免許税の軽減措置
- 不動産取得税の軽減措置
- 印紙税の軽減措置
- 固定資産税の減額措置
住宅ローン減税
住宅ローン減税は新築や中古住宅を購入した場合に適用される制度で、年末のローン残高の0.7%にあたる所得税が控除されます。新築の場合は13年間、中古の場合は10年間にわたり適用され、一戸建てだけでなく、マンションも住宅ローン減税の対象となります。
ただし、令和6年度の税制改正で、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。
登録免許税の軽減措置
登録免許税は、不動産の登記などにかかる税金です。主な軽減措置は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 軽減前 | 軽減後 |
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
令和6年度の税制改正で、住宅購入や住宅ローンに関する減税措置の適用期限は、2027年3月31日までとなっています。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、新築を建てた場合に発生する税金です。毎年支払う税金ではなく、購入時に1度だけ支払います。住宅の評価額から1,200万円を引いた額を課税標準額として、不動産所得税は計算されます。
軽減措置が適用されるには、建築した住宅の床面積が50㎡以上240㎡が条件です。税率は4%から3%まで軽減され、2027年3月31日までが適用期限となります。
印紙税の軽減措置
契約書や領収書などを作成した場合は、印紙税が発生します。不動産に関する契約書も課税の対象となります。軽減措置の対象となる契約書は、以下のとおりです。
| 契約書の種類 | 条件 |
| 不動産譲渡契約書 | 契約金額が10万円を超える |
| 建設工事請負契約書 | 契約金額が100万円を超える |
印紙税の軽減は、20〜50%程度で、金額によって軽減される額は異なります。適用期限される期間は、2024年4月1日〜2027年3月31日までとなっています。
固定資産税の減額措置
毎年1月1日時点で不動産を所有している場合は、固定資産税を納める必要があります。固定資産税は、住宅などの不動産を持ち続けている限り支払続ける税金です。
固定資産税にも減額制度があり、新築住宅にかかる3年間の固定資産税は、2分の1に減額されます。マンションの固定資産税も1/2減額され、期間は5年と新築住宅よりやや長めです。
新築から4年目、マンションの場合は6年目から、固定資産税の額が元に戻ります。適用される期限は、2026年3月31日までになります。
住宅購入で専門家の意見をどう利用するか
住宅購入の相談先には、不動産会社やハウスメーカー、ファイナンシャルプランナーなど様々です。それぞれの専門家が持つ知識やノウハウを活用すれば、住宅購入に関する不安や疑問を解消できるでしょう。
住宅購入に役立つ相談サービス
住宅購入には返済計画やローンの組み方など、考えることが多すぎて、何から手をつけていいかわからない方も少なくありません。そんな時は、以下のような相談サービスの活用を検討しましょう。
| 相談先 | 特徴 |
| 不動産会社 | 新築や中古など、幅広い物件を取り扱っている |
| ハウスメーカー | 土地探しや間取りについての相談ができる |
| ファイナンシャルプランナー | ライフプランを考慮した資金計画をアドバイスしてくれる |
| 銀行 | 住宅ローンの具体的な説明が受けらえる |
| 住宅相談窓口 | 特定の会社に偏らず、中立な立場で相談に応じてくれる |
これらのサービスの中には、無料で相談できるものもあります。まずは無料相談を利用して、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
住宅購入の無料相談で理想の家づくりを実現!相談前に準備しておくこともお伝えします
ファイナンシャルプランナーの役割と選び方
ファイナンシャルプランナー(FP)は、収支や税金、契約している保険などを整理して、ご自身やご家族のライフプランに合わせたお金のアドバイスをしてくれます。
具体的には、以下のようなサポートをしてくれます。
- ライフプランニングの設計
- 家計の見直し
- 住宅ローンの借り方や返済計画の設計
- 資産運用の方法を提案
- 保険の見直し
- 教育費や老後資金の準備方法
相談の際は、事前の準備が重要です。家計簿や通帳、給与明細などを用意しておくと、現状の経済状況がより正確に分析できます。
また、実績が豊富なファイナンシャルプランナーを選ぶことも大切です。経験が少ない相談員もいるため、実績や口コミをチェックしましょう。「話しやすかった」「わかりやすく説明してくれた」などの評価は、選ぶ際の重要な判断材料となります。
不動産会社から得られる重要情報
不動産会社は住宅ローンの申し込みから契約後の引き渡しまで、住宅購入における全体のサポートをしてくれます。新築物件だけでなく、中古物件やマンションなど幅広い物件を取り扱っているため、希望に合った物件を見つけやすいのが特徴です。
特に地域密着型の不動産会社は、エリアの物件情報に精通しています。大手にはない未公開物件の紹介や、周辺エリアの相場や環境に関しての詳しい情報が期待できます。
ただし、自分に合った不動産会社の数は多く、自分に合った会社を見つけるには時間がかかります。1社だけでなく、複数の会社を比較して検討すると良いでしょう。
まとめ
本記事では、住宅購入における資金計画の重要性や資金不足が招くリスク、返済額の決め方などを解説しました。住宅購入は人生での中で最も大きな買い物です。資金が不足していると、日々の生活が苦しくなってしまうため、購入後の失敗を防ぐには事前の準備が必要です。
ご自身の収支を把握したり、収入にあった住宅ローンを組んだりすると、購入後も安心して生活が続けられるでしょう。本記事を参考に、理想の家づくりに向けての準備を進めてみてください。
おうちの買い方相談室では、資金計画を含めたアドバイスをすべて無料で行っております。家計の見直しや将来の貯蓄方法のご提案もいたします。まずは、WEBやお電話からお気軽にお問い合わせください。