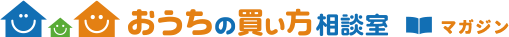注文住宅の値段はいくら?相場と内訳、予算別の特徴を徹底解説!
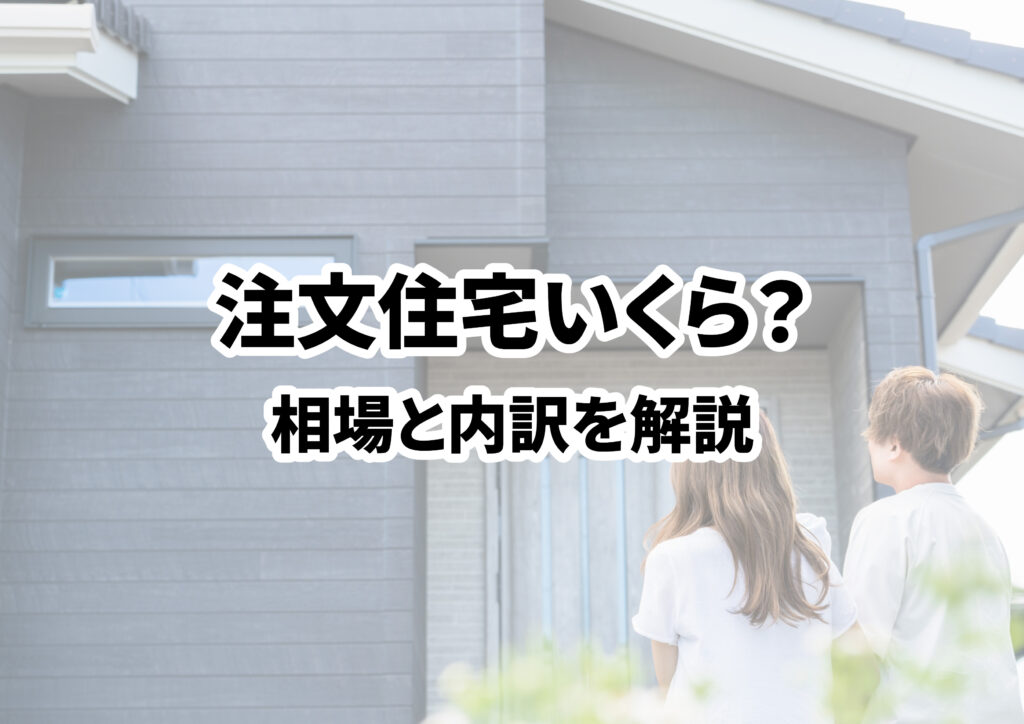
「いつかは自分たちの家を建てたい」と考えたとき、真っ先に気になるのが「注文住宅はいったい、いくらで建てられるのだろう?」という疑問ではないでしょうか。インターネットで調べても、専門用語が多くて分かりにくかったり、価格帯が広すぎて自分たちに合うのがどれか分からなかったりすることも多いです。
この記事では、これから注文住宅を建てたいと考えている方に向けて、必要な値段の相場や詳しい内訳、そして予算内で理想の家を建てるためのポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、漠然としていた注文住宅の値段のイメージが明確になり、具体的な家づくりの計画を立てる第一歩となるはずです。
注文住宅の値段、平均相場はいくら?
注文住宅の値段は、土地を持っているかどうかで大きく変わります。まずは「土地なし(建築費のみ)」と「土地あり(土地代込み)」それぞれの全国平均相場を見ていきましょう。公的なデータを参考にすることで、客観的な相場観を掴むことができます。
【土地なし】建築費のみの費用相場
すでに土地を持っている方や、親から譲り受けた土地に家を建てる(建て替え)場合の費用相場です。住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、注文住宅のみを建てる際の建築費の全国平均は3,861万円となっています。
土地代がかからない分、建物自体に予算をかけられる傾向があり、設備のグレードアップやデザインにこだわる方も多いようです。
| エリア | 建築費用の平均 |
| 全国 | 3,861万円 |
| 首都圏 | 4,190万円 |
| 近畿圏 | 4,142万円 |
| 東海圏 | 3,893万円 |
| その他地域 | 3,623万円 |
出典: 住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」
【土地あり】土地代込みの費用相場
これから土地を購入して注文住宅を建てる場合、建築費に加えて土地の購入費用が必要になります。国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査 報告書」によると、土地の購入資金を含めた注文住宅の全国平均取得価格は5,811万円です。
土地の値段はエリアによって大きく異なるため、全体の費用も地域差が顕著に現れます。
| エリア | 土地代+建築費の合計(平均) |
| 全国 | 5,811万円 |
| 首都圏 | 6,787万円 |
| 近畿圏 | 5,265万円 |
| 東海圏 | 4,810万円 |
出典: 国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査 報告書」、住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」を基に作成
地域によって値段は大きく変わる
上記のデータからも分かるように、注文住宅の値段、特に土地の価格は首都圏をはじめとする都市部で高くなる傾向があります。同じ予算でも、建てるエリアによって土地の広さや建物の大きさが変わってくるため、家を建てたいエリアの土地相場を事前に調べておくことが非常に重要です。
注文住宅にかかる値段の詳しい内訳
注文住宅の見積もりを見ると、「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」といった項目が出てきます。これらは家づくりにかかる総費用の重要な構成要素です。それぞれの内容を理解することで、見積もりの内容を正しく把握し、予算計画を立てやすくなります。
建物本体にかかる「本体工事費」
本体工事費は、建物そのものを建てるための費用で、総費用の約70%〜80%を占める最も大きな部分です。これには、基礎工事、構造躯体の組み立て、屋根や外壁、内装の仕上げ、基本的な設備の設置などが含まれます。広告などで見かける「坪単価」は、この本体工事費を基に計算されていることが一般的です。
家を建てるために必要な「付帯工事費」
付帯工事費は、建物本体以外で、快適に暮らすために必要な工事にかかる費用です。総費用の約15%〜20%が目安とされています。具体的な工事には以下のようなものがあります。
| 工事の種類 | 内容 |
| 外構工事 | 庭、駐車場、門、塀、アプローチなどの整備 |
| 給排水工事 | 上下水道管を敷地内に引き込む工事 |
| 地盤改良工事 | 土地の地盤が弱い場合に必要な補強工事 |
| 解体工事 | 建て替えの場合、古い家を取り壊す費用 |
これらの費用は土地の状況や家の設計によって大きく変動するため、本体工事費とは別に見積もっておく必要があります。
税金や手数料などの「諸費用」
諸費用は、工事以外で発生する手続き上の費用や税金のことで、土地代と建築費用を合わせた総額の約10%〜12%が目安です。 これらは現金で支払うことが多い費用のため、あらかじめ準備しておくことが大切です。
| 費用の種類 | 内容 |
| 各種税金 | 不動産取得税、登録免許税、固定資産税、印紙税など |
| 登記費用 | 土地や建物の所有権を登記するための司法書士報酬など |
| 住宅ローン関連費用 | ローン事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など |
| 保険料 | 火災保険料、地震保険料 |
【値段別】どんな注文住宅が建てられる?特徴と実例
ここでは、建築費の価格帯別に、どのような家が建てられるのか、その特徴を見ていきましょう。ご自身の予算感と照らし合わせながら、理想の家のイメージを膨らませてみてください。
1,000万円台:コストを抑えたシンプルな家
1,000万円台の注文住宅は、コストを重視する若い世代や、家以外の趣味や教育にもお金をかけたいと考える方に選ばれています。建物の形を凹凸の少ないシンプルな四角形(総2階建てなど)にしたり、屋根の形状を単純な片流れや切妻にしたりすることで、建築コストを抑える工夫がされています。
内装もビニールクロスを主に使用し、間取りもシンプルになりますが、その分、家具やインテリアで個性を出しやすいというメリットもあります。性能を落とすのではなく、設計や仕様を工夫することで、コストパフォーマンスの高い住まいを実現します。
2,000万円台:メリハリをつけて理想を叶える家
2,000万円台は、注文住宅を建てる上で最も多いボリュームゾーンです。 予算に少し余裕が生まれるため、こだわりたい部分とコストを抑える部分のメリハリをつけることで、理想の住まいを実現しやすくなります。
例えば、「キッチンはグレードの高いものにしたいから、他の部屋の内装は標準仕様にする」「断熱性能にはこだわりたいので、間取りはシンプルにする」といった予算配分が可能です。 すべての希望を叶えるのは難しいかもしれませんが、優先順位を明確にすることで、満足度の高い家づくりができるでしょう。
3,000万円台:こだわりの設備やデザインを実現できる家
全国の平均建築費に近い3,000万円台の予算があれば、多くの希望をプランに盛り込むことが可能になります。 デザイン性の高い外観にしたり、LDKの床を無垢材にしたり、最新のシステムキッチンやユニットバスを導入したりと、選択肢が大きく広がります。
間取りの自由度も高まり、吹き抜けや広いウォークインクローゼット、書斎など、ライフスタイルに合わせたこだわりの空間を実現しやすくなる価格帯です。ただし、要望を詰め込みすぎると予算オーバーになる可能性もあるため、どこに重点を置くかを見極めることが大切です。
4,000万円台:高品質で自由度の高い家
4,000万円以上の予算を確保できる場合、かなり自由度の高い家づくりが可能になります。中庭のあるコの字型の家など、複雑でデザイン性の高い設計も選択肢に入ります。
内装や外装には漆喰やタイルなどの高品質な自然素材をふんだんに使用したり、ホームシアターやビルトインガレージといった趣味の空間を取り入れたりすることも可能です。性能、デザイン、設備ともにハイグレードな、まさに「理想の家」を追求できる価格帯と言えるでしょう。
注文住宅の値段を左右するポイント
同じ延床面積の家でも、仕様によって値段は大きく変わります。コストを調整する上で、どのような要素が値段に影響するのかを知っておくことは重要です。
| ポイント | 内容 | コストへの影響 |
| 建物の形状と延床面積 | 凹凸の多い複雑な形状や、面積が広いほど高くなる | 大 |
| 設備のグレード | キッチン、バス、トイレなどのグレードが高いほど高価になる | 中 |
| 内装・外装材の種類 | 無垢材や漆喰、タイルなどの自然素材は高価になる傾向がある | 中 |
| 窓の数と性能 | 窓の数が多い、または断熱性・気密性の高い窓を選ぶと高くなる | 小 |
建物の形状と延床面積
注文住宅の値段に最も大きく影響するのが、建物の大きさと形状です。延床面積が広くなれば、その分だけ材料費や人件費が増えるため、価格は上がります。また、同じ延床面積でも、正方形や長方形のシンプルな形に比べて、凹凸の多い複雑なデザインの家は、外壁の面積が増え、施工の手間もかかるためコストアップの要因となります。
キッチンやバスなどの設備グレード
キッチンやユニットバス、トイレなどの住宅設備は、さまざまなメーカーから多様なグレードの商品が販売されています。標準仕様のものから、高機能なハイグレードモデルまで価格帯は幅広く、どのグレードを選ぶかによって費用は大きく変わります。特にこだわりたい設備はグレードを上げ、それ以外は標準仕様にするなど、メリハリをつけるのがおすすめです。
内装・外装に使う建材の種類
壁紙、フローリング、外壁材などの建材も価格に影響します。一般的に広く使われるビニールクロスや合板フローリング、サイディング材などは比較的安価です。一方で、漆喰や珪藻土といった塗り壁、無垢材のフローリング、タイル張りの外壁などを選ぶと、材料費も施工費も高くなる傾向があります。
注文住宅の予算を決めるときの3ステップ
最後に、無理のない予算を立てるための具体的なステップを紹介します。しっかりとした資金計画が、後悔しない家づくりの鍵となります。
STEP1:家づくりの総予算を把握する
まずは、家づくりにかけられるお金が総額でいくらあるのかを把握します。これは、ご自身の貯蓄などから出せる「自己資金(頭金)」と、金融機関から借り入れる「住宅ローン」の合計額で決まります。
STEP2:住宅ローンで借りられる金額を知る
住宅ローンでいくら借りられるかは、年収や勤務先、勤続年数などによって決まります。多くの金融機関では、ウェブサイトで手軽に借入可能額をシミュレーションできます。一般的に、無理なく返済できる借入額の目安は、年収の5倍〜7倍程度、年間の返済額が年収の25%以内とされています。
STEP3:無理のない返済計画を立てる
最も重要なのは、「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」を基準に予算を組むことです。住宅ローンの返済は長期にわたります。将来の教育費や老後資金なども考慮に入れ、余裕を持った資金計画を立てましょう。複数の金融機関のプランを比較検討し、ご自身のライフプランに最適な住宅ローンを選ぶことが大切です。
まとめ
注文住宅の値段は、土地の有無や建物の規模、仕様によって大きく変動しますが、全国平均では建築費のみで約3,800万円、土地代込みで約5,800万円が一つの目安です。家づくりには本体工事費の他に、付帯工事費や諸費用も必要になることを念頭に置き、総額で予算を考えることが重要です。
価格帯によって実現できる家の特徴は異なりますが、予算内で最大限の満足を得るためには、どこにお金をかけたいのか、家族で優先順位をしっかりと話し合うことが成功の秘訣です。この記事を参考に、あなたの理想の家づくりへの第一歩を踏み出してください。