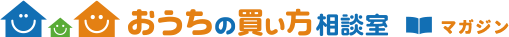注文住宅の費用相場解説!家づくりで必要なお金の内訳や費用を抑えるコツ
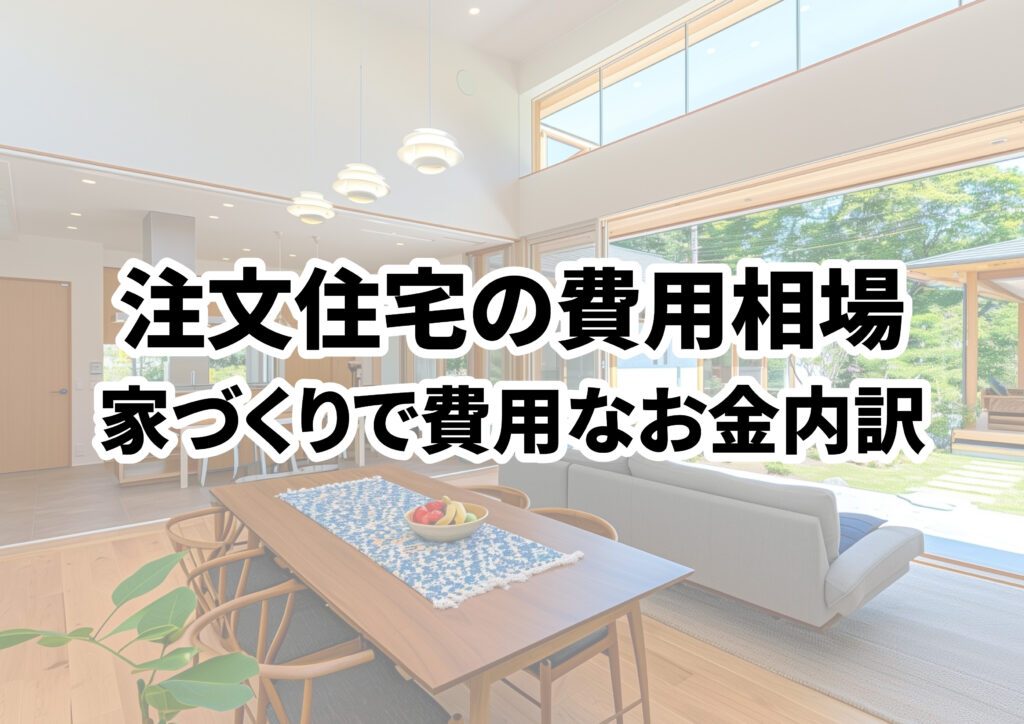
「自分たちのこだわりを実現できる注文住宅を建てたい」
「注文住宅は高いと聞くけれど、相場はどれくらい?」
「コストを抑えつつ、信頼できる会社に依頼するにはどうしたら良いのか」
デザインや間取りを自由に決められる注文住宅は、住宅購入する人にとっての憧れです。しかし、自由にできる分、わからないことも多く、不安に思っている方も少なくないでしょう。そこで本記事では、注文住宅の全国的な費用相場や必要なコストの内訳、予算決めのポイントなどを解説します。注文住宅を依頼する際の注意点や、建売住宅との比較も紹介するため、参考にしてください。
注文住宅とは
一戸建て住宅を購入する際、さまざまな購入方法があります。そのなかでも「注文住宅」とは、住む人(購入者)が自分の予算や生活スタイル、希望に合わせてデザインや間取りを自由に決めて購入する家のことです。
一般的には、ハウスメーカーや工務店、設計事務所に依頼して設計や施工を進めていきます。一からすべてを決めていけるため、家族構成や趣味、ライフスタイル、今後の人生設計を反映した家づくりができるでしょう。
細かなところまで決められる分、家の引き渡しまでには時間がかかるため、余裕を持った計画を立てる必要があるでしょう。また、魅力的な設備や素材を取り入れ過ぎると予算オーバーする可能性もあるため、注意が必要です。
しかし、注文住宅は購入した家に合わせて自分たちの暮らしをつくるのではなく、自分たちの理想とする暮らしに合わせた家づくりができるため、近年人気が高まっています。
注文住宅の費用相場とは
注文住宅は、自分たちに合わせた理想の家づくりができるため、「家を買うなら注文住宅にしたい!」と考えている方も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、必要になる費用です。注文住宅以外の価格相場もあわせて解説するため、比較しながら検討を進めてみましょう。
地域別の価格差について
注文住宅の購入に必要な費用は、建てる家の大きさ、使用する素材や設備、デザイン料などによって大きく異なる場合があります。費用の目安として、「2023年度フラット35利用者調査」をもとに相場を紹介しましょう。
なお、「フラット35」とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している全期間固定金利型の住宅ローンのことです。住宅ローンには金利が変動するタイプもありますが、フラット35は金利が返済期間中変わらず固定されるため、返済計画が立てやすいというメリットがあり、注文住宅の購入でも多く利用されています。
地域別都道府県別主要指標
| 住宅面積 | 敷地面積 | 建設費 | |
| 全国 | 119.5㎡ | 334.5㎡ | 3,861.1万円 |
| 首都圏 | 120.4㎡ | 232.7㎡ | 4,190.2万円 |
| 近畿圏 | 123.2㎡ | 251.0㎡ | 4,142.1万円 |
| 東海圏 | 121.0㎡ | 304.1㎡ | 3,893.4万円 |
| その他地域 | 118.0㎡ | 411.7㎡ | 3,623.8万円 |
この表からわかるように、注文住宅の費用相場は全国で3,861.1万円ですが、地域によって偏りがあります。その差は、相場が一番高い首都圏とその他地域では、約560万円です。
また、この金額は土地代を含めないもののため、土地を購入して家を建てる場合には、これ以上の費用がかかります。土地代も地価の高い都心部では、高くなる傾向にあるため、土地代を含めた費用相場の差は、さらに大きくなると考えられるでしょう。
坪単価の計算方法
住宅購入を検討していると、価格の指標として「坪単価」という言葉を耳にする方も少なくないでしょう。「坪単価で言われてもよくわからない」という方のために、坪単価について解説します。
坪単価とは、建築費用を「1坪あたりの金額」で示したものです。なお、1坪とは約3.3平方メートルの大きさで、坪単価の計算方法は、建物本体の価格を延床面積(坪数)で割ることで求められます。
たとえば、2,400万円の住宅が延床面積40坪であった場合、坪単価は「2,400万円÷40坪=60万円」と計算ができます。
住宅の規模と価格の関係
一般的に、建てる家が大きくなればなるほど、価格も上がりますが、必ずしもそうであるとは限りません。住宅の規模と価格が比例しない理由として、考えられるものの一例は、以下の通りです。
■スケールメリットが働く場合
規模が大きいとスケールメリットが働くこともあり、坪単価が割安になる場合もあります。たとえば、家の大きさに関係なくキッチンや浴室などの設備が必要です。しかし、これらは大きさに関係なく一定の費用がかかるため、家の大きさによって大幅な価格差がなく、大きな家でも費用がそれほど変わらないケースもあるからです。
■設計・仕様による価格差
家づくりでは、設計費用にお金をかけたり、複雑なデザインになったために工事費用が高額になったりする場合もあります。また、使用する資材や設備などによっても価格が大きく変動します。
そのため、小さな家でも細かなところにまでこだわり、高級なものを使用する場合は費用が高額になります。一方で、大きな家でも設計がシンプルでローコストなものを使用すれば、価格を抑えられるでしょう。
一般的なコストの内訳
注文住宅を建てる際に必要なコストは、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分けられます。それぞれの詳細には以下のものなどがあります。
【1】本体工事費(全体の約70~80%)
家を建てるために必要な費用です。全体の内訳としての多くを閉める本体工事には、土台・柱・屋根などの構造部分の工事から、外壁・内装・床材・窓などの工事、キッチンや浴室などの設備工事のすべてが含まれます。また、建設に関わる費用には、設計費も含まれます。
【2】付帯工事費(全体の約15~20%)
家づくりでは、家本体を建てるだけでなく、その他付帯工事にも費用がかかります。たとえば、購入した土地の地盤調査や上下水道・電気・ガスなどの引き込み工事、駐車場や庭などもある場合は、外構工事も必要です。
【3】諸費用(全体の約5~10%)
住宅購入には、さまざまな手続きがあり、それらにも費用が必要です。所有権移転・抵当権設定などの手続きにかかる登記費用、住宅ローンを組む場合は手数料や印紙代もかかります。さらに、もしものために備える火災保険や地震保険への加入も必要になるでしょう。
また、引っ越し費用も時期によっては高額になるため、あらかじめ予算に入れておくようにしてください。
建築会社による違い
注文住宅づくりでは、依頼する建築会社によっても価格差が出ます。価格差が出るポイントには、次のようなものがあります。
■会社の規模や間接コストの差
会社が大きければ、家づくりに使用する資材を大量発注して、コストを抑えられるため、住宅の価格を抑えられる可能性があります。
しかし、会社の規模が大きく、広告宣伝費用もかかっている場合や従業員が多い場合などは、広告費や人件費にも費用がかかっているため、逆に高くなる場合もあるでしょう。反対に広告費をかけていない小規模の工務店などでは、これらの費用がかかっていない分コストが抑えられる可能性があります。
■設計の自由度による差
注文住宅といっても、すべて自由に決められるものから、ある程度規格化されており、変更可能な範囲で希望を反映できるものまでさまざまです。ある程度規格化されているということは、その分の設計費用を抑えられたり、必要な資材を大量仕入れすることによるコストカットが可能になったりします。
■品質や管理体制などによる差
住宅づくりの費用は、現場管理の内容や職人の技術力も影響する場合があります。品質管理に力を入れている会社は、その分人件費や管理費が上がりますが、より安心して依頼できるというメリットもあるため、バランスをみて検討するとよいでしょう。
注文住宅の予算を決めるポイント
注文住宅に限らず、住宅購入を検討する際には、はじめに予算を決める必要があります。またこの予算決めが今後の家づくりやその後の生活に大きく関わっていきます。
ローン計画の立て方
住宅購入をする際、多くの方が住宅ローンを利用して、借入金を毎月返済していくことになります。住宅ローンには、事前審査があり、この審査を通過しなければ借入ができません。また、審査で借入限度額も決まるため、自己資金がない限り、その金額を超える住宅購入はできません。
一般的には、返済額(返済負担率)は、手取り月収の30%以内の金額に納めるのが、目安とされています。ただし、ローン計画で大切なのは、現在の経済状況だけをみて考えるのではなく、将来を見据えた計画です。
例えば、「今の家賃が10万円だから月々の返済は10万円以内であれば良いだろう」と考えたとします。しかし、今後家族が増えたり、子どもが進学したりすると、今より必要経費が増えるでしょう。そうなった場合、ローン返済が家計を圧迫する恐れがあるため、今後必要になってくるお金にも考慮した予算づくりが大切です。
カスタマイズの限界を知る
注文住宅は、一から自由に設計できるのが魅力ですが、予算さえあれば希望することが必ずしもすべて実現できるとは限りません。あらかじめ知っておくと良いことをいくつか紹介します。
■法的制限(建築基準法・都市計画法)
法的制限とは、建てられる建物の大きさ・高さ・構造に設けられている制限のことです。
【法的制限の例】建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の1階部分の面積)の割合のことで、建物の広さを制限する基準です。
例)建ぺい率が50%の場合、100㎡の土地では50㎡まで建物を建てることが可能
【法的制限の例】容積率
敷地面積に対する延べ床面積(全ての階の床面積の合計)の割合のことで、建物の高さを制限する基準です。
例)容積率が200%と定められている場合、100㎡の土地では200㎡の延べ床面積の建物を建てることが可能
【法的制限の例】用途地域
用途地域は、都市計画法のもと13種類に区分されており、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域などがあります。それぞれによって建てられる建築物に制限があります。
そのほか、隣地との距離や道路との接道義務などが影響する場合や、防火地域・準防火地域では、使用できる建材が制限されることもあるため注意しましょう。
コスト削減工夫の紹介
少しでも予算内で希望する家づくりをする場合、コスト削減がポイントになります。いくつか紹介するため、参考にしてみてください。
■優先順位をつける
どこにお金をかけるのか、事前に優先順位を決めておきましょう。優先順位を決めておけば、予算オーバーになってしまった時にどこから削っていくべきかが明確になります。
■窓の数を減らす
窓が多い方が日当たりも良くなるため、大きくしたり、数を多くしたりしがちですが、窓は意外に高くなるため、不要な窓を減らすのもコスト削減になります。必要なところを省くのではなく、窓がなくても問題のないトイレなどで検討してみるとよいでしょう。また、必要以上に大きな窓は室内の断熱性を損ねるため、適切なサイズを検討してください。
■バルコニーを大きくしすぎない
バルコニーが大きいとその分補強が必要になるため、コストがかかります。なんとなく広いバルコニーが魅力と感じる方も多いですが、本当に必要か検討するのも大切なコスト対策です。
■子ども部屋を小さくする
最近では、ワークスペースをリビングに設けて、子ども部屋は寝るために必要な最低限の広さのみを確保するという家づくりも増えています。コストカットだけでなく、家族がリビングに集まる工夫にもなります。
■外壁や屋根の面積を減らす
建物が複雑なつくりになると、外壁面積も増えます。面積が増えれば、施工費用がかかるだけでなく、今後のメンテナンス費用も高くなるでしょう。なお、屋根も同様に寄棟(よせむね)より切妻(きりづま)タイプの方が面積を小さくできるため、検討してみてください。
注文住宅の見積もり依頼方法
注文住宅をつくると決まった際、見積もりはどのように依頼すればよいのでしょうか。
見積もりは相見積もりが基本
見積もり取得の基本は、相見積もりです。相見積もりとは、見積もりを複数の会社から取ることをいいます。
【相見積もりのメリット】費用の妥当性がわかる
同じ項目の価格を比較すれば、相場がわかるようになります。
【相見積もりのメリット】内容やこだわりの違いがわかる
各社の仕様や使う資材の違い、アフターサービスなどがわかり、自分たちに必要なものの見極めができます。
【相見積もりのメリット】業者対応を比較できる
金額や規格だけでなく、安心して任せたいと思える会社選びもできます。
見積もりをとる際の注意点
見積もり取得する際は、相見積もりが重要ですが、見積もり取得時の注意点は、以下の通りです。
■相見積もりを取る際は同じ条件で取る
問い合わせする会社ごとに条件を変えてしまうと、比較ができなくなるため、予算や希望する家の条件は揃えた状態で取得しましょう。
■価格だけで判断しない
少しでも価格を抑え、同じ予算内でなるべくたくさんの要望が通る会社を選びたいと考えてしまいがちですが、品質や保証の良し悪しも大切なポイントです。バランス良く検討してみましょう。
具体的な要望の伝え方
注文住宅は、一から設計を決めていくため、「見積もりの段階では何を伝えれば良いのか?」と感じている方も多いのではないでしょうか。実際に注文住宅の場合は、設計が大方決まった段階で正式な見積がわかり、契約に進みます。
はじめの見積もり取得の段階では、予算や建設予定地、間取りの希望、こだわりたい部分(設備・デザイン・素材など)をわかる範囲で伝えましょう。また、イメージする家やデザインがあれば、それを提示するのもおすすめです。
比較対象としてのモデルハウス訪問
住宅購入を検討するために、モデルハウスを訪問するのもおすすめです。ハウスメーカーごとのデザイン性やこだわりが直接目で見られるため、自分たちのイメージや理想にあった会社選びができるでしょう。
ただし、モデルハウスを見学する際には注意点もあります。
モデルハウスに展示されている素材や設備は、そのメーカーにとって最高品質であることが多く、同じもので揃えると予算オーバーになる可能性があります。また、家全体の大きさも一般的な家よりも大きくつくられているケースが多いため、参考にしてつくったものの、実際に住んでみたら思っていたより小さいとなることもあります。契約前にこれらのポイントも確認して、依頼先を検討してみましょう。
注文住宅と建売住宅の違い
「注文住宅が魅力的だけど、予算のことを考えると躊躇してしまう」という方のために、注文住宅と建売住宅の比較をしてみましょう。それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、どちらが自分たちに向いているか、一度検討してみるのもおすすめです。
自由度やコストの比較
注文住宅は、一から設計を考えられるのが最大の魅力ともいえるでしょう。一方で、建売住宅は、すでにハウスメーカーや工務店が建てた家を購入することになります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| 注文住宅のメリット | 注文住宅のデメリット |
| ・間取りやデザインを自由に決められる
・住宅性能や設備を決められる ・建築段階もチェックできる |
・予算が高くなる可能性がある
・引き渡しまでの期間が長い |
| 建売住宅のメリット | 建売住宅のデメリット |
| ・注文住宅と比較して低コスト
・完成した家を見て決められる ・引き渡しまでの期間が短い |
・間取りや設備が選べない
・建設段階のチェックができない ・完成してから期間が経っている場合もある |
ランニングコストでの比較
住宅の維持に必要なランニングコストは、おもに固定資産税や火災保険・地震保険料、修繕費などがあります。また、そのほか光熱費もランニングコストに含まれるでしょう。
注文住宅と建売住宅で発生するランニングコストの差に大きな違いはありませんが、注文住宅では、光熱費対策として省エネ性能の高い設備や断熱材の導入によって、ランニングコストを抑えることも可能です。
一方で建売住宅は、カスタマイズができないため、省エネ対策を考える場合は、その仕様が適用されている家を探す必要があります。希望の立地・予算では断念しなければいけなくなる可能性もあるため、その点では注文住宅が有利となるでしょう。
長期的な価値を考える
注文住宅と建売住宅の長期的な価値を比較した場合、一概にどちらが良いということはありません。
注文住宅は、オリジナリティのあるオシャレなデザインの家がつくれる一方で、独自性が強すぎると資産価値が下がる可能性もあります。しかし、設備や性能にこだわった家であれば、その分資産価値が高まる可能性があるでしょう。
一方で建売住宅には、万人受けしやすい間取りやデザインが採用されているため、広く一般受けが良い家としての価値が高い可能性があります。ただし、導入されている設備や性能が低い場合は資産価値が期待できないこともあります。
そのため、売却の可能性がある場合は、自分たち以外の人にも価値のある家づくりが重要です。また、どちらの場合にも、定期的なメンテナンスを怠らないようにしておくことが大切です。
購入後のサポート体制の違い
引き渡し後に、万が一不具合やトラブルがあった際、注文住宅では、施工会社がアフターサービスを提供するのが一般的です。
また、建売住宅の場合は販売会社がアフターサービスを提供するケースもあります。ただし、建売住宅の場合は建築後期間が空き中古物件になってから購入した場合は、新築と同様のサポートが受けられない場合もあります。さらに、購入した物件を大幅リフォームしたりした場合にもサポート対象外になる可能性があるため、注意しましょう。
注文住宅を選ぶ際の注意点
最後に注文住宅を購入する際の注意点を解説します。
土地選びの重要性
注文住宅では、所有している土地に家を建てる場合を除き、土地探しもしなければいけません。土地探しをする際に、重要視するポイントとして、価格や立地が最優先となるでしょう。
しかし、これまでに解説したように土地には建ぺい率や容積率、用途地域などによる法的制限があります。安さに惹かれて購入したものの、満足のいく家が建てられないということがないように事前に確認して購入を検討しましょう。
また、日本は災害大国でもあります。水害や地震などのリスクがどのようにある土地なのか、ハザードマップで確認できるため、こちらも事前にチェックしておくようにしてください。
契約前に確認するべき事項
住宅購入では、基本的に一度契約書を交わした場合、キャンセルはできません。キャンセルできる場合も違約金が発生したり、キャンセルできる期間が決まっていたりするケースが多くあるため、契約に進む前に確認しておくべき事項です。
また、工事のスケジュール(着工日、竣工日、引き渡し日)も打ち合わせで聞いていた内容と相違がないか書面の確認を怠らないようにしてください。
さらに、支払スケジュールや住宅ローン特約、保証(アフターメンテナンス)の内容にも抜けや相違がないか必ず確認するようにしましょう。
プロジェクト全体のスケジュール管理
住宅購入では、土地探しから住宅の設計、施工に1年ほどの期間を要することも少なくありません。また、住宅ローンを利用する場合は、そちらの手続きも必要になるため、スケジュールや手続きが複雑に入り組み、把握が難しくなることも少なくありません。
しかし、全体の流れを把握しておかないと「●月までに引き渡しのはずだったのに、工事が遅れているとギリギリになって知った」「●月に平日にしかできない手続きがあるのに、休みを取る手配をしていなかった」などのトラブルが起こることもあります。
そのため、施工会社や金融機関の担当者と密に連絡を取り合い、進捗やスケジュール、タスクの確認を都度行うようにしましょう。
完工後のメンテナンスについて
注文住宅が完成し、住みはじめた後、3ヶ月、半年、1年、2年、5年、10年などの周期で、定期点検を実施するケースが多くあります。ここでお家の気になる部分があれば、担当者に伝えれば、保証の範囲で対応してもらえるでしょう。
また、ハウスメーカーや施工会社によっては、有償で10年後も定期点検を実施してくれるケースがあります。
そのほか、自身でもこまめに以上がないか点検したり、10〜15年単位で外壁や屋根の塗装をしたりする必要があります。安全な暮らしを守り、お家の価値を維持するためにも、メンテナンスは怠らないようにしてください。
まとめ
本記事では、注文住宅についての基本や全国の価格相場、家づくりに必要なコストの内訳などを詳しく解説しました。
注文住宅は、デザインや間取りを一から考えられるだけでなく、使用する素材や設備も自分好みにアレンジできるため、とことんこだわった家づくりがしたい方に向いている住宅購入方法です。しかし、土地には法的規制が定められているため、その範囲内で実現可能な家づくりを検討する必要があります。
また、自由に決められるがゆえに予算オーバーになることも少なくないため、予算や優先順位をきちんと決めてから、設計に進むようにして、無理なく理想の家を手に入れましょう。