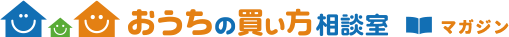注文住宅の諸経費はいくらかかる?内訳から相場、節約術まで専門家が徹底解説します!

「夢の注文住宅!でも、一体いくらかかるんだろう…」家づくりを考え始めると、まず気になるのがお金のことではないでしょうか。特に、建物本体の価格以外にかかる「諸経費」については、何にどれくらい必要なのか、総額でどの程度見ておけば良いのか、分かりにくいと感じる方も多いかもしれません。
この記事では、注文住宅の諸経費について、その内訳や相場、支払うタイミング、そして把握しておくべき重要なポイントを分かりやすく徹底解説します。諸経費への理解を深め、安心して理想のマイホーム計画を進めるための一助となれば幸いです。
注文住宅の「諸経費」とは?本体価格以外にどんな費用がかかるの?
注文住宅を建てる際には、よく目にする「坪単価」や「本体工事価格」だけでは家は完成しません。それ以外にも、様々な種類の費用が発生します。これらを総称して「諸経費」と呼ぶことが一般的です。
諸経費と混同されやすい費用に「付帯工事費」や「別途工事費」があります。これらは、建物本体以外で敷地内で必要となる工事(例:古い家の解体、地盤改良、外構工事、給排水・ガス・電気の引き込み工事など)にかかる費用を指します。
見積もりを見る際には、これらの費用が「諸経費」に含まれているのか、それとも別項目になっているのかをしっかり確認することが大切です。諸経費とは、主に手続きや税金、保険など、工事費以外の費用であると理解しておくと良いでしょう。
【重要】注文住宅の諸経費、主な内訳と費用の目安を徹底解説!
注文住宅の諸経費には、具体的にどのような項目があり、それぞれどれくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、家づくりのプロセスに沿って、主な諸経費の内訳と費用の目安を詳しく解説します。
土地購入にかかる主な諸経費(土地をこれから購入する場合)
土地探しから注文住宅を建てる場合には、まず土地の購入に関連する以下のような諸経費が発生します。これらは土地の価格や条件によって金額が大きく変わるため、注意が必要です。
参考資料)
国税庁 印紙税の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
国税庁 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書までhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
国税庁 No.7191 登録免許税の税額表https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
印紙税(不動産売買契約書)
土地の売買契約書に貼付する印紙の費用です。契約金額によって税額が異なり、国税庁の定める税額表に基づいて納めます。軽減措置が適用される場合もありますので、最新情報を確認しましょう。
登記費用(所有権移転登記など)
購入した土地の所有権を自分の名義に変更するための「所有権移転登記」や、住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」にかかる費用です。これには、国に納める登録免許税(税金)と、手続きを代行する司法書士への報酬が含まれます。
登録免許税は土地の評価額や住宅ローンの借入額によって変動し、司法書士報酬も依頼先によって数万円〜十数万円程度と幅があります。
不動産取得税(土地分)
土地や家屋などの不動産を取得した際に、都道府県から課される税金です。土地取得後、しばらくしてから納税通知書が送られてきます。税額は原則として「固定資産税評価額 × 税率」で計算されますが、住宅用地については大幅な軽減措置が設けられています。
固定資産税・都市計画税清算金
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。そのため、年の途中で土地の所有権が売主から買主に移る場合、引き渡し日を基準に日割り計算し、買主が売主へその年の残りの期間分を清算金として支払うのが一般的です。
建物建築にかかる主な諸経費
次に、実際に建物を建てる際に発生する諸経費です。これらも計画や建築企業によって内容や金額が変わってきます。
参考資料)
国税庁 No.7191 登録免許税の税額表https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
建築確認申請費用
建物を建てる際には、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかどうかの確認を受ける必要があります。この「建築確認申請」にかかる手数料です。申請手数料は建物の規模や自治体によって異なりますが、一般的には数万円〜十数万円程度が目安です。通常、ハウスメーカーや設計事務所が手続きを代行します。
設計料
建築家や設計事務所に設計を依頼する場合にかかる費用です。一般的には工事費用の10〜15%程度が目安とされますが、設計事務所の方針や業務範囲によって異なります。
ハウスメーカーに依頼する場合は、設計料が本体工事費に含まれていることが多いです。(この項目は個別の契約に基づくため、国が定める一律の基準はありません。)
地盤調査・改良費用
安全な家を建てるためには、建築地の地盤の強度が十分であるかを確認する地盤調査が必須です。調査費用は数万円程度が一般的です。調査の結果、地盤が弱いと判断された場合には、地盤改良工事が必要となり、その費用は工事の内容によって数十万円〜時には百万円以上かかることもあります。
これは見積もり段階では確定しづらい費用の一つです。(この項目も個別の調査結果や工事内容に基づくため、国が定める一律の基準はありませんが、建築基準法で地耐力に応じた基礎の構造が定められています。)
水道加入金・各種インフラ工事費
新たに水道を利用するために、自治体に支払う負担金(水道加入金や分担金などと呼ばれます)が必要です。金額は自治体や水道メーターの口径によって異なります。また、敷地内への上下水道管やガス管の引き込み工事、電気の引き込み工事などにも別途費用がかかります。
引用元:各自治体の水道局・下水道局のWebサイト(例:東京都水道局「給水申込納付金・手数料」など。お住まいの自治体の情報をご確認ください。)
登記費用(建物表題登記、所有権保存登記など)
新築した建物を法務局に登記するための費用です。具体的には、建物の物理的な状況(所在地、構造、床面積など)を示す「建物表題登記」(土地家屋調査士へ依頼)、誰の所有物であるかを示す「所有権保存登記」(司法書士へ依頼)などがあります。これらにも登録免許税と専門家への報酬が必要です。
住宅ローン利用にかかる主な諸経費
住宅ローンを組む際にも、以下のような様々な費用が発生します。金融機関や選択するローン商品によって内容や金額が大きく異なるため、複数の商品を比較検討することが重要です。
参考資料)
国税庁 No.7191 登録免許税の税額表https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
融資事務手数料
住宅ローンを借りる金融機関に支払う手数料です。
「定額型」(数万円程度)と「定率型」(借入額の2.2%程度など)があり、金融機関や商品によって設定が異なります。定率型の場合、借入額が大きいと手数料も高額になります。(この項目は金融機関の規定によります。)
ローン保証料
住宅ローンの返済が万が一滞った場合に、保証企業が金融機関へ返済を肩代わりするための費用です。支払い方法には、借入時に一括で支払う「一括前払い型」(借入額や返済期間に応じて数十万円~百万円程度)と、毎月のローン金利に上乗せして支払う「金利上乗せ型」(金利に0.2%程度上乗せなど)があります。
最近では保証料が不要な住宅ローンも増えています。(この項目は金融機関や保証企業の規定によります。)
抵当権設定登記費用
住宅ローンを借りる際、金融機関は購入する土地と建物に抵当権を設定します。これは、万が一返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を売却して貸付金を回収できるようにするためです。この抵当権設定登記にかかる費用で、登録免許税(借入額 × 0.4%が基本ですが、住宅の場合は軽減措置あり)と司法書士への報酬が必要です。
諸経費はいつ支払う?タイミングと流れを把握して資金準備を!
注文住宅の諸経費は、一度にまとめて支払うわけではありません。土地の契約から建物の完成、そして入居後まで、家づくりの様々な段階で支払いが発生します。資金計画を立てる上では、いつ、どの程度の現金が必要になるのかを事前に把握しておくことが非常に重要です。
【土地契約時~引き渡しまで】土地関連費用の支払い
土地を購入する場合、まず土地の売買契約時に「手付金」(売買価格の5〜10%程度が一般的)を支払います。また、不動産企業への「仲介手数料の一部(半金など)」をこのタイミングで請求されることもあります。「印紙税(不動産売買契約書)」も契約書作成時に必要です。
その後、土地の残金決済・引き渡し時には、「土地代金の残金」、「仲介手数料の残金」、「所有権移転登記費用」、「固定資産税・都市計画税の清算金」などを支払います。この段階でまとまった現金が必要になることが多いです。
【工事請負契約時~着工まで】建物関連費用の初期支払い
建物の工事請負契約時には、「契約金」(工事費用の10%程度が一般的)をハウスメーカーや工務店に支払います。この契約書にも「印紙税」が必要です。「建築確認申請費用」や、設計事務所に依頼している場合は「設計料の一部」などもこの時期に発生することが多いです。
【工事中】中間金や地盤改良費など
工事の進捗に合わせて、「着工金」や「中間金」(それぞれ工事費用の30%程度など)を支払う場合があります。これは契約内容によって異なりますので、事前に工事代金の支払いスケジュールをしっかりと確認しておきましょう。地盤改良工事が必要になった場合は、その費用もこの時期に支払うことが多いです。
【建物完成・引き渡し時】多くの諸経費が発生する最終段階
建物が完成し、引き渡しを受ける際には、最も多くの種類の諸経費の支払いが発生します。
具体的には、「工事費用の残金」、「建物の登記費用(表題登記、所有権保存登記)」、「住宅ローン関連費用(融資事務手数料、ローン保証料を一括で支払う場合、抵当権設定登記費用など)」、「火災保険料(一括払いの場合)」、「水道加入金」などです。住宅ローンの実行もこのタイミングで行われ、自己資金と合わせて各種支払いに充当されます。
【入居後】忘れてはいけない税金の支払い
入居してからも支払う必要がある諸経費があります。代表的なものは「不動産取得税」で、入居後数か月してから都道府県から納税通知書が届きます。
また、「固定資産税・都市計画税」は、家を所有している限り毎年課税されます。これらの税金についても、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。
注文住宅の諸経費に関する重要ポイントと注意点
諸経費に関して事前に知っておくべき重要なポイントや注意点をいくつか解説します。これらを理解しておくことで、資金計画の精度を高め、後悔のない家づくりにつながります。
諸経費の多くは「現金」での準備が必要
住宅ローンは、主に土地代金や建物本体工事費に充当されることが一般的です。そのため、登記費用、各種手数料、税金、保険料といった諸経費の多くは、住宅ローン実行前に現金で支払う必要があると認識しておくことが重要です。
特に、土地の契約時の手付金や仲介手数料、工事請負契約時の契約金などは、比較的早い段階でまとまった現金が必要になります。自己資金がどれくらい必要になるのかを事前に正確に把握し、しっかりと準備しておくことが、家づくりをスムーズに進めるための大前提となります。
見積書の内容を徹底確認!「諸費用一式」に注意
ハウスメーカーや工務店から提示される見積書には、どこまでの諸経費が含まれているのかを必ず詳細に確認しましょう。単に「諸費用一式」と記載されている場合でも、具体的にどの項目が含まれ、何が含まれていないのかをリストアップしてもらい、明確にすることが大切です。
含まれていない費用があれば、別途自分で概算金額を計算し、総予算に漏れなく組み込む必要があります。この確認を怠ると、後から想定外の出費に慌てることになりかねません。
予期せぬ出費に備え「予備費」を確保しておく
家づくりでは、どんなに綿密に計画を立てていても、予期せぬ追加費用が発生することがあります。たとえば、地盤調査の結果、想定よりも大規模な地盤改良工事が必要になったり、工事中に仕様変更をしたくなったり、選んだ設備が廃盤になり代替品が高額になったりするケースです。
このような不測の事態に備えて、総予算の中に「予備費」として、ある程度の金額(一般的には建物工事費の5〜10%程度など)を別途確保しておくことを強くおすすめします。予備費があれば、万が一の際にも慌てず対応でき、計画の変更や妥協を最小限に抑えることができます。
諸経費も住宅ローンに含められる?条件と注意点を理解
「諸経費を支払うための現金が足りない…」という場合、諸経費も住宅ローンに含めて借り入れできるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、金融機関や住宅ローン商品によっては可能です。一部の金融機関では、土地代金や建物本体工事費に加えて、登記費用や火災保険料、住宅ローン手数料などの諸経費もまとめて借り入れできる「諸費用ローン」や「諸費用一体型住宅ローン」といった商品を取り扱っています。
まとめ 注文住宅の諸経費をしっかり把握して計画的な家づくりを!
注文住宅の諸経費は多岐にわたり、その総額も決して小さなものではありません。諸経費への正しい理解と事前の準備が、後悔しない注文住宅を実現するための非常に大切な第一歩となるでしょう。この記事が、あなたの素晴らしい家づくりのお役に立てることを心より願っています。