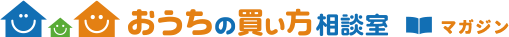地域別注文住宅の価格相場を徹底解説!住まいの予算事例
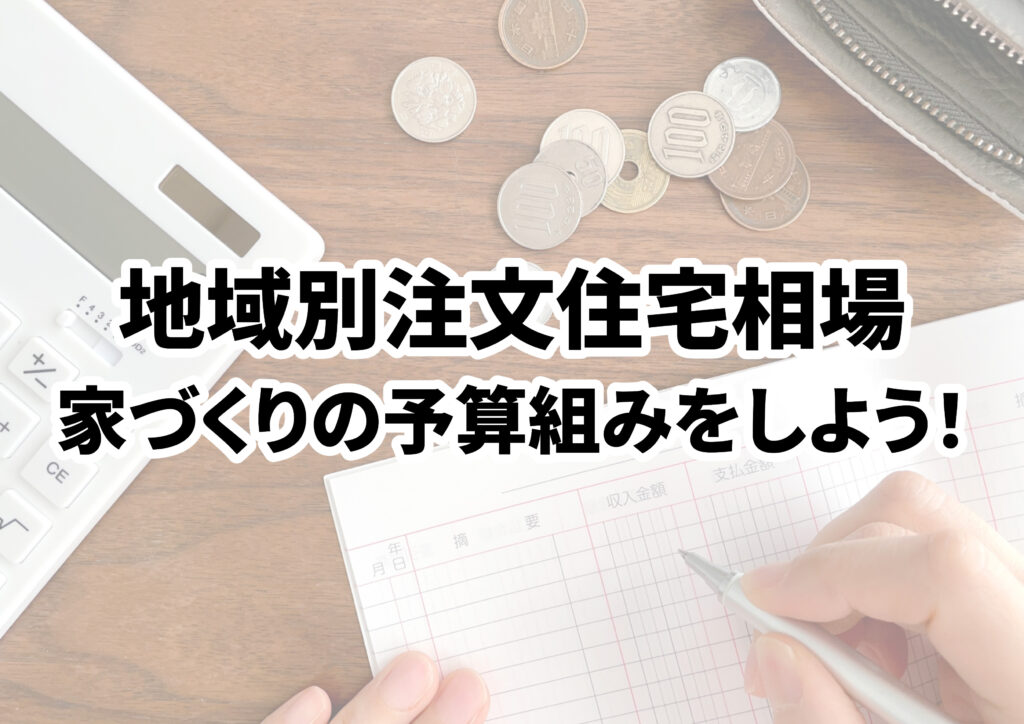
「戸建の購入を検討しているものの、注文住宅か建売住宅どちらを買うべき?」
「注文住宅は大体どれくらいの予算が必要?」
「失敗しない家づくりのポイントは?」
住宅購入を検討する際、デザインや間取り、設備を一から決められる注文住宅で理想の住まいづくりをしたいと考える方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、注文住宅のメリットや引き渡しまでの流れ、一般的な費用相場、設計プランづくりのポイントなどを詳しく解説します。
注文住宅とは?戸建購入の検討に必要な基本知識
「そろそろ家を購入したい!」「家を買うなら戸建がいい!」と考える理由はさまざまですが、結婚や出産をはじめとしたライフスタイルの変化をきっかけに考えるようになる方も多いのではないでしょうか。
しかし、家を買うと漠然とした目標を立てたものの、住宅購入に必要な知識がなく、何から学んだり検討したりしていけば良いのかわからずお困りの方も少なくないでしょう。そこで、まずは戸建で人気の「注文住宅」について、基本的な知識を身につけましょう。
注文住宅と建売住宅の違い
戸建の購入には、いわゆる誰も住んだことのない新品の家である「新築」もしくは、「中古」のいずれかを選択しますが、新築のなかにも「注文住宅」と「建売住宅(分譲住宅)」があります。それぞれがどのようなものか以下で詳しく解説します。
注文住宅とは
注文住宅は、施工するハウスメーカーや建築会社と建築工事請負契約を結び、一から設計プランを考えてもらって家を建てる購入方法です。住宅の設計から予算などの条件内で自由に家づくりができるのが魅力といえるでしょう。
また、設計だけでなく、床材や壁紙の種類、コンセントの位置からお家の設備など、住宅をつくるためのさまざまなことを考えられます。なお、注文住宅を購入する際は、すでに建設予定の土地を所有していない場合、土地の購入からスタートしていきます。
建売住宅とは
建売住宅は分譲住宅ともよばれるもので、不動産会社などの住宅の売主と売買契約を結んで土地付きの住宅を購入するものです。なお、土地付きの住宅を購入するのが建売住宅ですが、すでに建物が経っている状態で購入するケースもあれば、建設予定の段階で購入する場合もあります。
建設予定もしくは建設中の場合は、一部の内装や設備を自分たちの希望でカスタマイズできる場合もあります。
注文住宅のメリットとデメリット
注文住宅のメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
注文住宅のメリット
注文住宅の最大のメリットは、先述の通り設計の段階からすべて自分たちの意見を反映しながら家づくりができることにあるでしょう。
設計図の作成などの専門的な作業は、それぞれの専門家が行うものの、外観・内装のデザイン、間取り、細かな設備選びやその配置など、基本的に依頼する建築会社やハウスメーカーにお任せしない限りは、自分たちで考えることができます。
そのため、住宅購入にあてる予算の配分も自分たちで考えられるため「設備にお金をかけたい」「デザインにとことんこだわりたい」「キッチンに予算を多く割きたい」などが可能です。また、プランができてからも設計する過程を見れるため、実際に家ができてきた際に気になる部分が出てきた場合などにも柔軟に軌道修正できるケースもあります。
注文住宅のデメリット
家づくりの過程を自分たちで決められるのがメリットである一方で、人によってはすべて考えなければいけないのが負担と感じることもあるでしょう。注文住宅では、土地探しから設計まで、基本的には専門家にお任せするものの、自分たちの意見が必要になります。
さらに住宅購入する際には、あらかじめ予算を設定するケースが一般的ですが、注文住宅では設計プランを考えていると、どんどんやりたいことが増えていき、予算が増えていくことも少なくありません。そのため、予算に余裕を持たせておくか、かなえたいことに優先順位をつけて予算との兼ね合いを考えながら決めていく必要があります。
また、一から考えていくということは、それだけ時間も必要です。そのため、「住宅購入したい」と考えはじめてから、住宅の引き渡しまでに多くの時間を要することになります。場合によっては1年もしくはそれ以上の期間が必要になるケースもあるため、余裕を持って行動しなければいけません。
建売住宅のメリットとデメリット
建売住宅は、土地や住宅の価格がすでに決まった状態で販売されているため、購入を決めたものの、価格が変わる心配がありません。また、多くの場合がすでに住宅ができた状態で販売されているため、完成した家を見て購入を検討できるのもメリットといえるでしょう。
そして注文住宅が、土地購入から住宅の引き渡しまでに多くの時間を要するのに対して、建売住宅は比較的早く購入できます。早ければ1ヶ月程度で、引き渡しが完了するため、さまざまな事情から早く新しい家に住みたい場合にも適しているでしょう。
ただし、解説の通りすでに出来上がっているもしくは、建築プランができている家を購入するため、基本的には自分好みにカスタマイズできません。また、同じようなデザインの家を量産することでコストを抑えているケースも多いため、注文住宅より低予算で購入できるものの、オリジナリティのある家に住みたい場合には向いていないと考えられます。
注文住宅の購入がおすすめのケース
注文住宅と建売住宅それぞれのメリット・デメリットを考えると、注文住宅の購入がおすすめのケースは次に該当するケースです。
■こだわりを反映した家に住みたい
■自分たちで決めることが苦にならない
■予算に余裕がある
■新しい住居に住むまでの時間に余裕がある
上記に当てはまる場合は、注文住宅で理想の住まいづくりをするのがおすすめです。
注文住宅の建築プロセス
注文住宅が引き渡されるまでの大まかな流れを順番に解説します。なお、住宅購入はここで解説すること以外にも決めることや契約手続きなどが多くあるため、詳しく調べて進めていくようにしてください。
【1】予算や希望を考える
まずは、住宅購入にかける予算を検討します。予算は、今後のライフプランや支出も加味しながら無理のない金額を設定しましょう。そして、住宅購入によってかなえたいことをイメージして具体的な希望を考えます。
【2】土地を探す
土地がすでにある場合を除き、家を建てるための土地探しをします。通勤・通学を考慮したり、ハザードマップを確認したりしながら検討していきましょう。
【3】依頼する建築会社やハウスメーカーを選ぶ
住宅の設計や建築をお願いする会社を選定しましょう。ホームページなどで施工実績を見ながら自分たちの理想に近い実績が多くある会社に相談してみるのがおすすめです。
【4】住宅のデザインや間取りを設計して見積書を作成してもらう
打ち合わせでは住宅購入でかなえたい希望をなるべく具体的に伝え、それを設計プランに盛り込んでもらい、プランがある程度決まったら、見積書も作成してもらいます。
【5】建築プランがまとまり、予算に合意したら工事請負契約を締結する
建築プランが大方まとまり、提示された予算にも納得できたら、いよいよ契約を結びます。
【6】住宅ローンの本審査を行う
住宅ローンを組んで住宅購入する場合は、同時にローン審査も実施します。なお、ローンにははじめに仮審査があり、それを通過した場合にのみ本審査を受けられます。本審査が通ったら契約手続きに進みましょう。
【7】着工
諸々の手続きが完了したら、ついに建設開始です。工事に立ち会ったり、建設途中の現場を見学したりして、工事が順調に進んでいるか確認し、修正が必要な場合は担当者に相談しましょう。
【8】完成(竣工)後、住宅の引き渡し
無事に住宅が完成したら、引き渡しです。引っ越しは繁忙期と重なると、希望の日程でできない可能性があるため、早めに依頼しておいてください。
初めての家づくりで注意すべきポイント
注文住宅を購入する際に気をつけたいポイントの一例を紹介します。しっかり抑えて、後悔のない住宅購入をしましょう。
土地選びは慎重に
住宅を購入したら、多くの場合は長くその土地に住むことになります。そのため、土地選びは現在の状況だけで判断するのではなく、将来的なことも見越して選定しましょう。例えば、子どもが進学した場合の通学の便、周辺環境の変化などもすべてを把握することは不可能でも、考えられる範囲で検討材料に入れておくのがおすすめです。
さらに土地には、都市計画法に基づくさまざまな建築制限があるため、自分たちが建てたい住宅が問題なく建てられる土地であるかどうかもチェックしましょう。
デザインにこだわりすぎない
設計プランを考えるさい、参考にするウェブサイトやSNSを見ているとおしゃれなデザインに目がいきがちです。しかし、デザインを重視しすぎると、生活導線が確保できていない、設備が不十分、手入れが大変などの問題が住んでから出てくる恐れがあります。デザインも生活のしやすさもバランス良く取り入れましょう。
建設中や内覧会で不備がないかきちんとチェックする
どれだけ慎重に作業していても、担当者同士の連携ミスなどによって、施工ミスが起こる可能性があります。また、プラン通り進められていても「実際に現場で見たらちょっと修正を加えた方が良い」と思うこともあるでしょう。そのため、引き渡し前に何度かチェックするようにして、住んでから不備を見つけることのないようにしてください。
注文住宅の費用構造を知ろう
住宅購入の際、多くの方がお金のことを不安に思うのではないでしょうか。注文住宅では、おもに「土地取得費用」「建築費用」「諸費用」などが発生しますが、それぞれについて詳しく解説します。
土地代と建築費の内訳
注文住宅では、建設費用のほかに土地の購入費用が必要です。これらのバランスは、ケースにより異なりますが、土地に3〜4割、建物が6〜7割程度使用するのが一般的とされています。
しかし、同じ予算でも地価の高いエリアで購入するのであれば、土地の比率が高くなるでしょう。一方で郊外など比較的地価が安いエリアであれば、建築費用にゆとりを持った予算を設定できます。
そのため、土地選びではどこに立地に予算を割きたいのか、住宅そのものに予算を割きたいのかも考慮して検討するとよいでしょう。
付帯工事費や諸費用について
住宅購入では、土地や建物本体にかかる費用以外にも多くの手続きにお金が必要になります。また、家を建てるだけでなく、土地内の外構などの付帯工事にも費用がかかるケースもあるでしょう。
なお、諸費用には次のようなものがあります。
・不動産取得税
・不動産会社仲介手数料
・登録免許税
・住宅ローン手数料
・表示登記費用
・印紙代(印紙税)
・火災保険料
など
住宅ローン手続きについて
住宅購入では、多くの方が住宅ローンを組んで、30年や35年かけて返済していくことになるでしょう。住宅ローンは、さまざまな金融機関がプランや金利を設定していますが、いずれの場合も大まかに2種類の金利タイプに分けられます。
固定金利
固定金利とは、その名の通り金利が固定され変わらないタイプの住宅ローンです。
なお、固定金利には借入する方が選択した期間中、金利が固定される「固定金利期間選択型」と返済全期間の金利が固定される「全期間固定型」があります。
「固定金利期間選択型」の期間は、金融機関によってさまざまですが、3年、5年、10年、15年、20年などのなかから選択できるのが一般的です。選択した期間が終了したあとは、変動金利に切り替えるか、再び固定金利期間選択型にするかを選べます。
変動金利
変動金利は、固定金利とは異なり、銀行の短期プライムレートによって、随時金利が変動するタイプの住宅ローンです。市場や経済の動向によって当初の見立てより返済の総額が高くなるリスクはあるものの、現状では固定金利よりも低金利で借入ができるため、多くの人が変動金利を選択しています。
それぞれのメリットとデメリットを理解して、自分たちの返済計画にあったプランを選択しましょう。
地域別の注文住宅の相場を比較
費用の内訳などを解説しましたが「結局のところ、注文住宅を購入するにはどれくらいの費用が必要なの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。購入費用は地域によっても異なるため、それぞれの目安をご紹介します。購入の参考にしてみてください。
都市部と地方での相場の違い
住宅金融支援機構の調査によると、2023年度における土地付き注文住宅の費用相場は、全国平均4,903万円でした。なお、前年度からは200万円ほど増加傾向にあります。
さらにエリア別でみると、購入費用の相場は次のような結果となりました。
| 土地購入あり | 土地購入なし | 土地購入費用 | |
| 全国平均 | 4,903万円 | 3,863万円 | 1,498万円 |
| 首都圏平均 | 5,680万円 | 4,195万円 | 2,277万円 |
| 東海圏平均 | 4,811万円 | 3,897万円 | 1,319万円 |
| 近畿圏平均 | 5,265万円 | 4,142万円 | 1,851万円 |
| その他エリア平均 | 4,299万円 | 3,625万円 | 915万円 |
この結果からも分かるように、首都圏と首都圏・東海圏・近畿圏エリア以外の購入費用相場には、1,000万円以上の差があることがわかります。ただし、差が出る要因は建物の建築費用ではなく、土地代の差です。
建築費の動向
昨今、さまざまなものの価格が高騰しており、生活を圧迫していますが、価格の高騰は建築業界でも深刻な問題です。国土交通省が公表している「令和6年度 住宅経済関連データ」によると、首都圏の住宅建築費用の動向は次のように推移しています。
| 調査年(年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 建築費(万円) | 3,206 | 2,964 | 3,061 | 2,958 | 3,558 | 3,301 | 3,510 | 4,077 | 5,050 | 5,466 |
| 延床面積(㎡) | 132.7 | 113.7 | 113.3 | 120.4 | 116.9 | 117.2 | 113.1 | 125.0 | 143.4 | 133.4 |
| 建設費単価(万円) | 24.2 | 26.1 | 27.0 | 24.6 | 30.4 | 28.2 | 31.0 | 32.6 | 35.2 | 41.0 |
資料:「住宅市場動向調査」(国土交通省)
建築費用には、材料費だけでなく人件費なども含まれますが、いずれも上昇傾向にあるため、10年間で1,000万円近い価格高騰がみられます。また、今後も価格の高騰が続く可能性もあるため、市場の動きにともなって建築費用は変動していくでしょう。
ライフスタイルに合ったプランづくり
注文住宅の購入を検討中の方に役立つプランづくりの事例をご紹介します。
家族構成と予算に応じた間取りの選び方
お家の間取りは、予算に合わせて可能な範囲で考えることになりますが、家族の人数によっても適切な部屋数が変わってきます。予算ありきで検討する必要がありますが、参考にして考えてみましょう。
■夫婦2人暮らしの場合
リビングやキッチン・ダイニングのほかに寝室を設けるのが基本になりますが、予算や広さに余裕がある場合は、それぞれの仕事や趣味に使える部屋を取り入れるのがおすすめです。
■夫婦と子ども1人の場合
1部屋を寝室、1部屋を子ども用が必要になりますが、もう1部屋を夫婦が自由に使える部屋として確保する3LDKがおすすめです。1部屋余裕があれば、今後家族が増えても安心です。
■夫婦と子ども2人の場合
一般的に主寝室と子ども部屋2つの計3部屋が必要になるため、3LDK以上の間取りになるでしょう。スペースがあれば、1部屋余分に和室などを取り入れれば、来客時にも活用できます。
いずれの場合も、家族の生活スタイルやライフステージの変化に対応できるような工夫があれば、何年経っても快適な暮らしができるため、予算の範囲内で計画してみましょう。
エコ住宅やZEH住宅の費用と効果
長期的に必要なコストを重視するのであれば、設備にこだわった家づくりもおすすめです。近年温暖化による気温上昇によりエアコンの使用頻度が増えていると感じている方も多いでしょう。一方で、光熱費の高騰により、家計が圧迫されています。
対策として、断熱性能の高いエコ住宅にすることで、エアコンの使用量が抑えられるようになり、光熱費の節約につながる可能性があります。
また、ZEH(ゼッチ)住宅も近年増えていますが、このZEH住宅とはNet Zero Energy Houseの略で、お家の屋根に設置する太陽光発電で電力を創出したり、省エネルギー設備や外皮の高断熱利用などを導入したりすることによって、消費エネルギーよりも創出エネルギーが上回る住宅のことです。
これらの住宅は、国や自治体からの補助金制度が設けられている場合もあるため、一度調べて導入を検討してみてはいかがでしょうか。
注文住宅の会社選びのポイント
ここまでに注文住宅のメリットや検討のポイントになる内容を解説してきましたが、最後に理想の住まいづくりをかなえるための会社選びについて解説します。
信頼できる施工業者の探し方
注文住宅では、設計から建築までの行程を一括で依頼するケースも多く、後悔しない家づくりには、依頼先選びが重要なポイントになります。信頼できる施工業者として、全国展開していたり、CMでもよく目にしたりする大手ハウスメーカーに依頼する方法もありますが、必ずしもその選択が自身の家づくりにとって正解とは限りません。
自分たちが理想とする住まいのイメージの家づくりが得意な会社や、着工後に軽微な修正などに柔軟対応してくれる会社、アフターサービスが充実している会社など、それぞれの会社に強みがあります。そのため、どのような住まいが理想なのかを考えて、信頼できる施工業者を探していくことが大切です。
また、住宅購入を検討する際、まずは住宅展示場を見学しにいく方も少なくありません。しかし、展示場にある家はあくまでも展示用であり、実際の家の広さよりも大きくつくられている場合もあります。そのため、展示されている家だけを見て決めるのではなく、そのハウスメーカーが実際に建てた家を訪問したり、見学させてもらったりするようにしましょう。
業者選びのための比較ポイント
業者選びに困ったときは、以下の比較ポイントを参考に、候補を絞り込んでみるのもよいでしょう。
■デザインの得意分野
■販売価格の相場
■対応している工法や設備、性能など
■引き渡し後の保証やアフターサービスの内容
■技術や使用する素材の質
また、このほかに営業担当者との相性も家づくりには重要なポイントです。「不安なことが聞きやすい」「要望をしっかり汲み取ってくれる」「やり取りがスムーズにできる」などの観点からも検討してみましょう。
契約時の注意事項とトラブル回避法
住宅購入は人生で一番高額な買い物と言われるほど、たくさんのお金が必要になります。そのため、後悔やトラブルなく購入するためには、以下の内容を確認しながら契約手続きを進めましょう。
■設計図面・仕様書の内容
工事請負契約書を締結すると、金額だけでなく設計内容にも同意したことになります。そのため、打ち合わせで決めた内容が図面や仕様書に正しく反映されているかを確認してください。専門用語や設計図でわからないことがあれば納得いくまで担当者に説明してもらいましょう。
■工事見積書の中身と金額
見積書は設計図や工事の工程と照らし合わせて、問題がないか確認する必要があります。不足があった場合、後々追加費用の請求が発生し、トラブルになるケースもあるため、注意してください。
■工程表や工事が遅延した際の対応
やむを得ず工事が遅延した場合、仮住まいなどに発生する追加費用が保証されるかどうかも重要な確認事項です。工事に遅れが生じるとトラブルになる可能性がある場合は、特に注意してください。
■キャンセル時の条項(違約金など)
基本的に契約書を交わした後のキャンセルはできません。しかし、何かしらの理由でどうしてもキャンセルしなければいけなくなった場合、どのような対応になるのかも念のため確認しましょう。
■保証やアフターサービスの内容
丁寧に作業していても、受け渡し後にトラブルが発生する場合もないとは限りません。その際に施工業者の保証範囲で対応してもらえない場合は、有償になるため、保証やアフターサービスの内容も把握しておいてください。
まとめ
今回は、注文住宅を購入する際の基礎知識や注文住宅のメリット、購入費用の内訳や相場などを解説しました。
注文住宅はお家のデザインや間取り、設備を自由に決められるため、こだわりの住まいをつくりたいと考える人におすすめです。予算をもとにこだわりたいポイントの優先度を決め、信頼できる業者と共に理想の住まいを実現させてください。なお、一からお家をつくりあげるため、引き渡しまでには時間がかかるため、余裕を持って計画するようにしましょう。